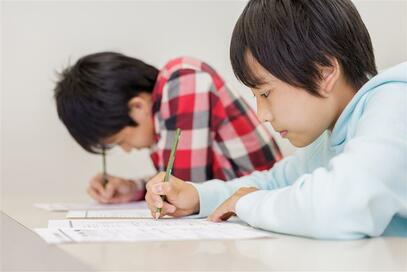暦の上では秋ですが、まだまだ気温が高い日が続きそうです。冷房をつけることが欠かせませんが、冷えすぎによる体調不良、いわゆる「冷房病」の恐れもあることから、注意が必要です。そこで今回、環境面や栄養面から冷房病を予防する方法について、内科医・血液専門医の久住英二先生に詳しく教えてもらいました。
すべての画像を見る(全5枚)「冷房のあたりすぎ」が招くさまざまな体調不良
冷房病とは、正式な病名ではありませんが、冷房のあたりすぎによって生じる体調不良全般を指します。
おもな症状は、冷え、だるさ、食欲低下、便秘、肩こり、頭痛、腰痛、むくみなど。
ずっと冷房の効いた部屋にいると、生活が不活発となりますが、それによって次のことが生じます。
・血流の停滞
・気分の落ち込み
・体温を管理する自律神経の働きが乱れる
これらの複数の要因によって症状が起きます。
冷房病が悪化すると、やせやうつ病、不眠などの重い症状に至ることもあるため、日頃から室内環境を整え、体調管理を行いましょう。
室温を下げすぎると高まる「感染症リスク」
冷房の温度設定は、室温と外気温との差が5℃以内になるよう調整し、冷えすぎないようにしましょう。たとえば、気温32℃の日であれば、室温が27℃程度になるように冷房の強さを設定します。
ただし、今年はとくに暑い日が多いので、温度差が5℃以上になってしまいますが、あまり室温が高いと冷房する意味がないので、仕方ありません。
室温が低すぎると、夏風邪リスクも高まります。ウイルスや細菌に対する防御反応が鈍くなり、免疫力の低下を招く可能性もあるためです。
冬に風邪をひきやすいのと同様、室温が低いと鼻が冷え、ウイルスを排除する仕組みが働きにくくなり、感染症にかかりやすくなります。
●急激な温度変化にも注意
また、屋外の猛暑から冷房の効いた室内に急に入ったり、出たりをくり返すと、体温を調節する自律神経が適応しきれず、体温調節がうまくできなくなります。
体が冷えすぎ、冷房病の症状につながってしまいます。内外の気温差が大きくなりすぎないよう工夫することが大切です。
冷房のあたりすぎで便秘気味になることも
この時期、便秘気味になる場合には、入浴、運動、食事で対策しましょう。
入浴時はシャワーですませず、41℃以下の湯温でゆっくりつかりましょう。これにより、自律神経の副交感神経の働きが優位となり、胃腸の動きが増します。
運動も自律神経の働きを正常化して、胃腸の働きを増す効果があります。朝夕の涼しい時間帯に、ほんの10分程度軽いジョギングや、室内でのスクワットなどが取り入れるのもオススメ。夜はストレッチをしましょう。
食事は、胃腸の働きを高めるために、温かいみそ汁やスープを飲むのが理想的です。ショウガや根菜類が体を温める効果があるといわれています。
また、野菜で食物繊維をとることも便秘解消に有効です。