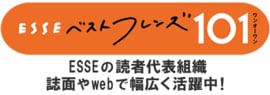70代になると意識し始めるのが、老後のお金や終活のこと。栃木県・益子でカフェ「猫車」を営んでいた信田良枝さんも、69歳で店を閉めてからは家計簿をつけ、それまでのお金の使い道を見直したそう。ですが、いわゆる老後2000万円問題や、将来のことにあせったり不安を感じることはなかったとのこと。今回は、日々1日1日を大切にして生きる信田さんの、今を大切にする考え方についてご紹介します。
※ この記事は『77歳 365日の紡ぎ方: 益子暮らし、元カフェ店主 信田良枝さんの居場所 』(主婦と生活社)より一部抜粋、再構成のうえ作成しております
すべての画像を見る(全3枚)お金は少したりないくらいがちょうどいい
69歳でカフェを閉じ、今後の暮らし方についてつらつらと考えていたときのこと。
世間では老後2000万円問題が騒がれていましたが、「煽られる感じが不愉快でしたね。足元を見つめて一日一日を納得して生きていればなんとかなる」と焦らなかったと信田さんは言います。
「その後、ひとり暮らしが始まり、私はいったいひと月いくらぐらいで生活しているんだろう? と疑問に。そこで、せめてランニングコストを把握しておこうと、家計簿をつけ始めました。お金の見える化です。すると、節約の余地があることに気づいたのです」(信田さん、以下同)
早速、光熱費を見直します。たとえば、あちこちにつけている照明は、白熱電球からLED電球に交換。消費電力が低いため、初期投資はかかりますが、長い目で見るとローコストです。
冷蔵庫もファミリータイプから1人用の小さなものに。下が冷凍室、上が冷蔵室のシンプルなつくりで、かえって使い勝手がよくなったと言います。電子レンジは故障をきっかけに手放そうと考えたそうですが、肉や魚の解凍に不便なため、単機能タイプを新調しました。
次に見直したのは、車の維持費です。燃費が悪く、自動車税の高い外国車から国産の軽自動車に乗り換えました。こちらも小回りがきいて、運転がラクに。
「キッチン家電も自動車も、身の丈に合うサイズや機能は扱いやすく、暮らしが快適になったのは驚きでした。
益子は陶芸の町。私の夫も陶芸家でした。結婚当時、生活はラクではなかったけれど、“お金をかけない豊かな暮らし方”をたくさん学びました。板と角材があればテーブルや本棚、がんばればベッドだってつくれます。そこには助け合いが生まれ、よい仲間もたくさんできます。
経験上、思うのです。お金はありすぎても、なさすぎても、人は荒廃します。“ちょっとたりない”くらいがちょうどいいのかな、と」