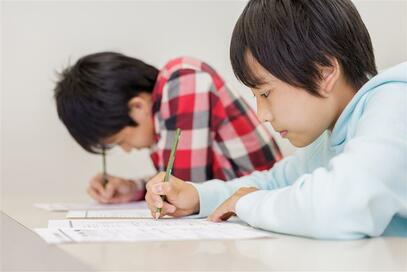母のために納戸を片づけ。タンスは残す
すべての画像を見る(全8枚)ここで私がすべきことは、母に今さら「捨てていなかったの?」と聞くことではなく、母が納戸にあるものを必要とするときのために、納戸を片づけること。
そのときの納戸は入り口すぐの足元にものが置いてあり、それを避けながら奥へ入るため、足が弱って杖をついて歩いていた母にとっては危なかったんです。そこで、安全に通りやすく、探しやすく、取りやすくなることを意識して片づけました。
タンスを反対側の壁に移動させ、納戸の入り口すぐの足元にはなにもなく安全な状態に。杖をついていても、そのまま奥まで一直線に歩ける通り道を確保しました。
日用消耗品のストックも、それぞれ使う場所に置かれていましたが、納戸に一か所にまとめて収納。家じゅうを歩きまわらなくても、納戸にさえ来れば必要なものを選べるようにしました。
捨てることだけが「片づけ」ではない
今回、納戸で見つけたのは私の幼少期のタンスでしたが、こうした大きな家具を捨てられないという高齢者は多いと思います。
たとえば婚礼タンス。子ども世代(30~50代)からすると「倒れたら危ない」「捨ててほしい」と思うかもしれません。でも思い出のつまったものは、そう簡単に捨てられるものではないんですよね。だからこそ、捨てる以外の選択肢も考えてほしいなと思います。
片づけの目的は捨てることではなく、住む人の心身を守り暮らしを向上させること。あくまでも捨てることはその手段のひとつです。大きな家具も「安全な場所に移動させる」「上段と下段に分ける」といった手段で暮らしが安全で快適になるなら、それも立派な片づけです。