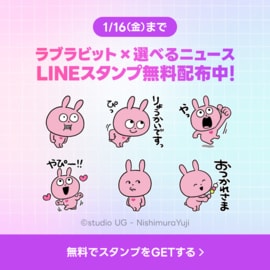「遺品整理」というと、孤独死やゴミ屋敷といったネガティブで特殊なイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、核家族化と高齢化が進む現代では、離れて暮らす家族や親戚の遺品を整理することは、特別なことではなくだれもが直面し得る課題です。その実態を事前に知っておけば、いざというときの備えにもつながります。そこで今回はグループ合計で18万件の実績をもつ「遺品整理プロスタッフ」の代表取締役社長・石田毅さんに「遺品整理」にまつわるリアルなお話を伺いました。
時間と労力がかかる「遺品整理」のリアル
そもそも遺品整理とは、ただ片付けたり清掃をするだけの作業ではありません。
「故人が生前に使っていた品々(衣服や家具など)、貴重品や思い出の品(写真、手紙)などを仕分けし、整理・片付け・処分することが遺品整理です。僕たち専門業社は、遺族の方の気持ちに寄り添いながら、処分することで供養になるよう努めています」(石田さん・以下同)
遺品をただ捨てるだけではないと知ると、少し安心される方もいるかもしれません。しかし、家の片付けや整理を経験したことがある人ならわかるように、ものを仕分ける作業ほどやっかいなことはありません。ましてや、持ち主がいないものの「いる・いらない」を判断するのは、時間と労力がかかるものです。
そのため、遺品整理プロスタッフのような専門業者に依頼される人も近年増えているそうです。
●取っておきたいものは事前に持ち出しておく
遺品整理で、「いる・いらない」の判断を業者に任せるのは難しいものです。そのため、依頼者が事前に現場で業者とすり合わせを行うことで、仕分け時のトラブルを防ぐことができます。
「基本的には、依頼人の方に見積もり、もしくは作業日に1度現場にお越しいただくことをお願いしています。その際に、そのままの状態でも大丈夫ですが、事前に『取っておきたいものを持ち出しておく』とさらに助かります。そうしていただければ問題が起きにくく、後悔も少ないと思います」
とはいえ、ものが多ければ多いほど、すべてを確認することが難しい場合もありますよね。そんなときは、抱え込まずにプロの力を借りる方法も。
「業者に取っておいて欲しいものを伝えていただければ大丈夫です。たとえば、『現金や貴金属、写真があったら取っておいて』など、ざっくりとしたジャンルでも問題ありません。ここでコミュニケーションを取ることで、このあとの片付けをスムーズに進めることができます」
また、とりあえず取っておいてもらい、片付け後に判断することも可能です。そのため、迷うものは分けておいてもらうように依頼しておきましょう。もちろん、片付け時に現場で立ち会うこともできます。
「ただし、確認時間が増えてしまう可能性もあるため、かえって作業時間がかかり料金が割高になってしまうこともあります。お問い合わせや見積もりの段階で、具体的な要望や疑問点を業者に伝え、確認しておくことが大切です」