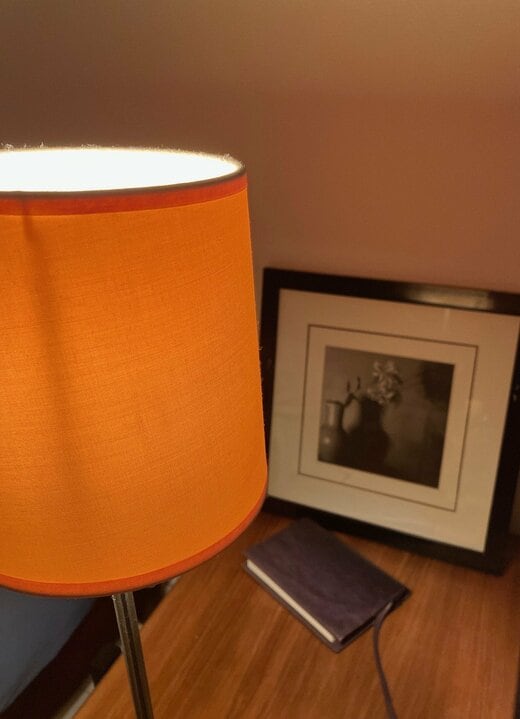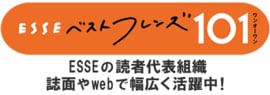進学・就職・結婚などで子どもが巣立つと、「荷物を残す・残さない」問題に悩みますよね。ここでは、ものをおおよそ手放した人の考え方や基準をご紹介します。元祖節約主婦として知られる若松美穂さん(50代)にお聞きしました。
すべての画像を見る(全4枚)家にある子どもの荷物、残す?残さない?
ともに子育てをしてきた仲間たちも、進学・就職・結婚などで、子どもたちが家を出ていくようになりました。わが家も同様です。巣立ったあとは、子どもたちの荷物をとっておくのか、手放すのか、悩ましいところでしょう。
さまざまなタイプの方がいると思うのですが、私はどちらかといえば思い出のあるものに固執しすぎないスタイルです。
●変化を受け入れ、子ども部屋も次のステップに移行
今まであったものがなくなり、ともに暮らしていた人がいなくなる。そのことに寂しさはあったとしても、それは「慣れていないから」と思うことにしました。なにせ子どもの成長はうれしいことですから。
周囲の話を伺うと、ものが残っていると、いつまでも子ども部屋は子ども部屋のままとして残っているようです。そのため、私はできるだけ暮らしの変化を受け入れ、少しずつ次のステップに移行する姿勢をとりました。
「わが家からの卒業」と考え、ものを減らすようになる
長女がひとり暮らしを始めたのは5年ほど前。あまりにも仕事が忙しくしんどそうで、「職場の近くに住みたい」と家を出ました。この時点で私は、「実家に泊まる場所はあっても、戻ってくるところはないですよ」というスタンス。わが家からの卒業ととらえていました。
ですが、長女が選んだ住居は都内のワンルーム。持って行けるものには限界があります。部屋はそれほど広くないですし、使わないものに囲まれて暮らすわけにはいきません。その時点ではまだ、わが家に残っているものも多かったと思います。
●LINEや帰省時のやりとりで「いる・いらない」を判断
そののち近畿地方へ転勤が決まり、やや広い部屋に引っ越すことに。収納場所もあるので、おおよそのものを持って行ってもらいました。家にあるものを新調するのはもったいないですし、「〇〇があったよね?」と探す手間をゆだねられるのも避けたかった。また、「とりあえず置いておいて」と言いたくなる気持ちもあると思ったからです。
その間に、こちらも片付けを決行! 帰ってくるたび「これはいる?」「あれはいる?」と聞いて、必要なものを持って行ってもらったほか、LINEで写真を送って、いるかいらないかを質問。さらにものを減らす工夫をしました。