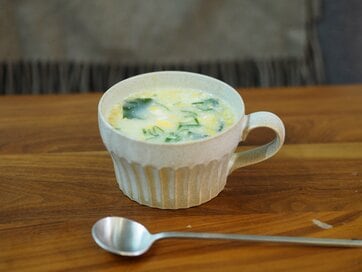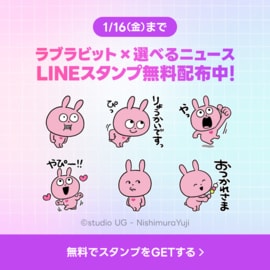私たちの生活に身近な存在である昆虫、アリ。そんなアリがじつは“しゃべる”ことをご存じですか? 「トトトトトトトト」「ワンワンワン」「ギュギョギュ」…これらはすべて、アリの発する音声です。“アリ先生”として活躍する岡山理科大学教授・村上貴弘さんは、パナマで採集したアリの音声を夜な夜な解析し、ついには自分もアリ語で寝言を言ったという仰天エピソードのもち主。ここでは地味だけど刺激的な研究の日々と、アリ語について教えてもらいました。
※ この記事は『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』(扶桑社刊)に掲載された内容を抜粋・再編集しています
すべての画像を見る(全4枚)アリの「言葉」を解析する方法
パナマで録ってきた音のファイルは合計で70ファイルほど。ここから、いよいよ「音のリスト」をつくり、音の頻度を解析していく。
まず音のリストだが、アリをシリアルで埋めてみたとき、幼虫と一緒のとき、働きアリの数を変えたとき、アリをピンセットでつかんだときなど、刺激やシチュエーションに対する反応だと明確にわかる場合に出す音に限定して拾っていく。
ほかの由来のわからない音に関しては、今回は解析から除外した。
ひとり、録音・録画データを確認しながら、行動や刺激と音の対応を記録していく。もちろん、音響データのなかにはただのノイズもある。アリの音かどうかを聞き分け、どの行動に対して発せられた音なのかを判断していく。
アリは単純な1音を重ねているだけではなく、1個体のアリがさまざまな音を組み合わせてコミュニケーションをとっているように聞こえる。3個体がやりとりしていれば、いくつもの音が重なるときもある。ひとつひとつ音を切り分け、どんな音なのかをまずはカタカナで表現してメモを取る。その作業は次のようなものになる。
1m44・571~1m44・827 キュ 1回
<音源がはじまってから1分44秒571~1分44秒827の間に「キュ」を1回>
2m17・842~2m18・064 ピッ 1回
<音源がはじまってから2分17秒842~2分18秒064の間に「ピッ」を1~回>
賢明な読者の方は、この秒数を見ただけでお気づきだと思う。たった0.2秒、0.3秒の間に発せられた一音を拾っているということに。それを945分!
ピュなのかピッなのか、人によって判断がズレてはいけないので、だれかと手分けをすることはできない。たったひとり、人力で最初の道筋をつけなくてはならない。膨大なデータを前にしてあまりにも途方がない。
しかし、なにがつらいって「正解がない」ことだ。もちろん、事前に音をたくさん聞き、自分のなかでルールは定めている。けれど、途中で自信がなくなる。
「これはこの行動ではないのか?」「ピュだと思ったけどピッなのか?」
ルールが揺らげば、今一度データを最初から聞き直す。
賽(さい)の河原のすみっこで、イヤホンをしながら「ピロピ 3回」とメモを取っている村上のもとに、心のなかから鬼の村上が現れて「これは、最初からやり直すでやんす」。
ガラガラガラガラ
そこまで積み上げていたデータはまっさらに真ったいら。うずくまる僕。気を取り直してもう一度解析し直すが、同じようなところでまた鬼の村上がひょっこり顔を出す。
「やり直したほうがいいぞ」
ガラガラガラガラ
何度も何度も何度もふりだしに戻っては基準づくりをする。これを地獄と言わずして、なんというのか。
●15分で7700回の音を発する「おしゃべりすぎる」アリも
さらに、強烈だったのは現地で「これは大変な解析になるかも」と予感していた、あのおしゃべりなハキリアリちゃんがいたファイルだ。そのファイルは、15分間でなんと7700回もの音を発していた。
15分間で7700回、1分間に513回、1秒間に8回以上! なにに不満があるのか、いやなことでもあったのか、ぶつぶつぶつぶつとキノコ畑の上でなにかをつぶいている。
「そんなに愚痴をこぼすなよ」
そうぼやきながら、解析を続けた。結局、たったひとつの15分のファイルを解析するのに1か月以上かかってしまった。