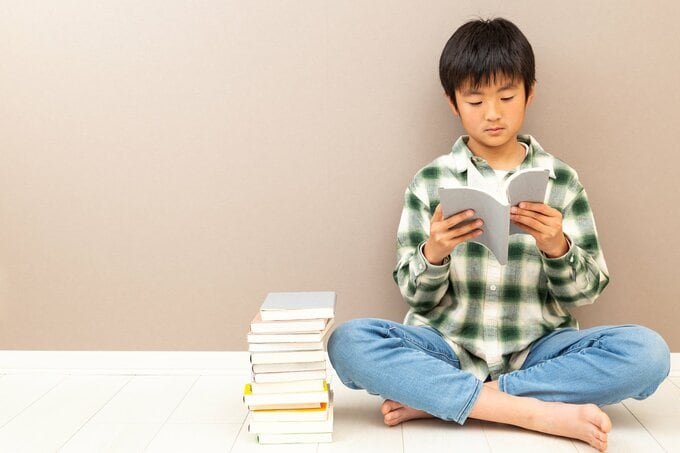「ムツゴロウさん」から受けた影響
すべての画像を見る(全5枚)僕は本のなかである人と出会い、深く共感した。それは、今の道につながるものだった。それがムツゴロウさん―― 畑正憲(はたまさのり)さんだ。
多くの人にとっては、ムツゴロウさんといえば、1980年から2001年の20年余りにわたって年に1~2回、フジテレビ系列で放送された『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』がおなじみだろう。
ムツゴロウさんが北海道の道東にある浜中町につくった「ムツゴロウ動物王国」と、中標津町につくった「ムツ牧場」を舞台にしたドキュメンタリー番組だ。
しかし、僕が初めてムツゴロウさんを知ったのは、テレビではなく本であった。父親が「ほら、好きそうな本があったぞ」と無造作に手渡してきた単行本が『ムツゴロウの無人島記』であった。小学6年の春。この本が大変におもしろかった。
この本は、畑さん一家が、東京から北海道浜中町の沖合にある無人島「嶮暮帰島」に1971年から1年間移住した記録である。
無人島に家族で暮らすというだけでもロマンいっぱいなのに、その島でヒグマの「どんべえ」やエゾタヌキの「マリ」、ホシボソガラスの「九郎」たちと、一緒に生活をするというのだから、おもしろくないわけがない! 夢中で読んだ。そしてこう思った。
「こんな大人がいるなんて、世界はまだまだ捨てたもんじゃないかもしれない」
●ムツゴロウさんの本を読みあさる日々
そこからむさぼるようにムツゴロウさんの著作を読みあさった。まずは動物関係の書籍だ。『どんべえ物語』『ムツゴロウの動物王国』などなど。読んでも読んでも、興味深い動物たちの生態や行動が出てくる。
とくに好きだったのが『天然記念物の動物たち』に出てくる、モリアオガエルの話だ。ムツゴロウさんはモリアオガエルの卵塊を求め、岩手に向かい、初夏の森に入る。
ウグイスの声、白い花でハネを休める赤い蝶、水の香り、アオモリトドマツの間にびっしり生えるエゾザサ──。
歩みを進めるごとに変わる景色の描写は美しく、読んでいる僕も一緒に探検をしている気持ちになった。毒虫に刺され、道に迷うムツゴロウさんの行く手を案じ、ページをめくるたびにドキドキした。そして、ついに見つけたとき、僕の心もざわめいた。
大学院生時代、実際に野外でモリアオガエルの卵塊を見つけたとき、「これか!」と小学校6年生当時の気持ちがありありと蘇ってきた。この目で見たモリアオガエルの卵は、ムツゴロウさんが言うように「生命のふくらみ」そのものであった。
●衝撃を受けた、ムツゴロウさんの「自然観」
ムツゴロウさんの本はほぼ網羅したが、もっとも僕に影響を与えたのは、ムツゴロウさんの自然観だ。詳細は不確かだが、こんなエピソードだったと記憶している。
あるとき、動物王国に電気を引かなくてはならなくなり、あまりの手間にスタッフは「自前で発電させるほうが簡単じゃないですか?」と畑さんに言う。
しかし、畑さんが強く主張したのが、「いや、それではダメなんだ。僕はこの動物王国を社会から隔絶されたものにしたくない。電気も水道もちゃんと引く、社会の一員としてきちんと支払うものは支払い、手続きをするときは手続きをしていかないと、この活動は意味がない」ということだった。
このやりとりは、世を憂う小学6年生にとって痛烈なカウンターパンチであった。僕も動物王国やムツ牧場は、社会から逃れた場所、自然のなかに引きこもれる場だと思っていた。
でも、畑さんはまったくそんなことを想定していない。そしてこう突きつける。
「動物愛護とか自然保護とかは、人の経済活動としっかり結びついてこそ、しっかりした根を張るのだと私は確信している」(『ムツゴロウ動物王国の四季』より)