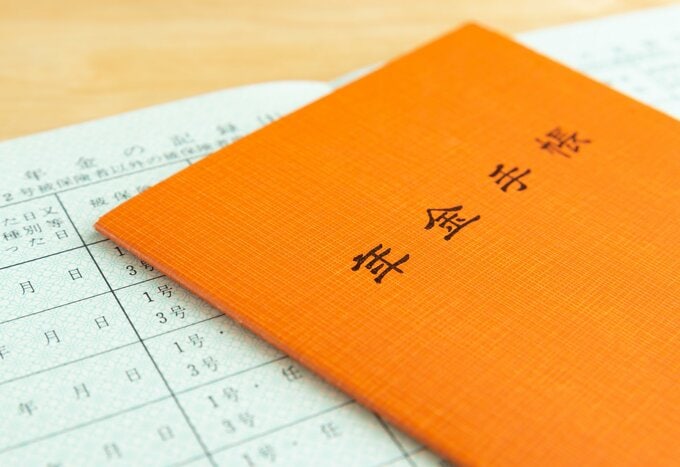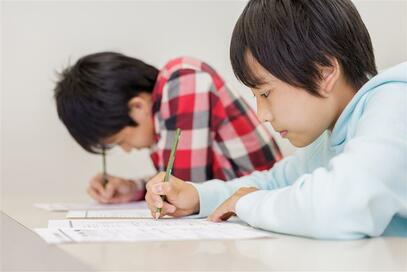家計を支えている人が亡くなったとき、残された家族が受け取れる年金が「遺族年金」です。遺族年金は、「家族の収入の減少分を補てんする大切なもの」と、相続実務士で、多くの書籍の監修を務めている「夢相続」代表の曽根恵子さんは話します。今回、遺族年金の種類や受け取り方、支給金額について、曽根さんに話を聞きました。
※ この記事は『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』(扶桑社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。
すべての画像を見る(全4枚)遺族基礎年金は「配偶者」と「子ども」がもらえる
故人が生前に公的年金に加入していた場合、遺された遺族は遺族年金を請求することが可能です。公的年金には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2種類があり、遺族年金も「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族年金は、故人が加入していた年金の種類や家族構成によって、支給の有無や支給額が異なるので注意が必要です。
まずは、原則として国民全員が加入することになっている国民年金から支給される遺族基礎年金について説明します。
遺族基礎年金を受け取れるのは、配偶者と、18歳に到達する年度の3月31日までの子どもです。子どもの年齢ですが、たとえば2025年9月に18歳になる子どもであれば、2026年3月31日までが対象となります。
配偶者がもらう場合は、子どもが18歳に到達する年度の3月31日まで、子どもがもらう場合は自身が18歳に到達する年度の3月31日までが支給期間となります。
配偶者といっても、子どもがいなければ遺族基礎年金はもらえません。子どもがいても、子どもが18歳を超えている場合も対象外です。
子どもがいない場合は、故人が国民年金の保険料を3年以上納付していれば「死亡一時金」が支給されます。保険料の納付期間は、しっかり確認しておきましょう。