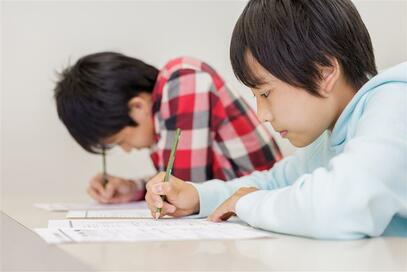片付けをするとき、つい「もったいない」と思ってしまったり「私は片付けられないんだ」と自信をなくしてしまうことはありませんか? 実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして、片付けに関する情報発信などを行っているつうさん(40代)も、以前はこうした考えに悩まされ、片付けが思うようにいかなかったそう。ここでは、つうさんが「手放してラクになった」と感じる、片付けに対する3つの考え方について語ります。
すべての画像を見る(全4枚)1:なんでも「もったいない」と思うのはやめる
片付けることが苦手だった頃の私は、片付け始めるとすぐに「もったいない」という言葉が浮かんできていました。なので、「使わないな」と思うようなものでも、いっさい捨てずにとっておく。それらをあいているスペースにどんどん押し込み、ものはさらに増えていき、そして、「どうすることもできない」と長年悩んでいました。
何度片付けようとしても出てくる「もったいない」という言葉。じつは、一緒に暮らしていた祖母の口ぐせでした。祖母はどんなものに対しても「もったいない」と言っていたので、使わずしまい込んだスーパーのビニール袋は、45リットルのゴミ袋で軽く5袋分はありました。
ほかにも紙袋、お菓子が入っていた缶、ビン、さらには食品トレイまでも。それぞれ何十個、もしくはそれ以上あり、家はゴミ屋敷に。
祖母はものに対してなんにでも「もったいない」というフィルターで見ていたので、どんなものでも捨てるということはできず、家の中がものであふれていったのです。
あるとき私は「心地よくない、暮らしにくい空間で何年も生活を続けていることはもったいなくないのかな?」と疑問をもつように。「本当に大切にしたいものは?」と自分自身に問うと、祖母とは違い、心地よさや空間でした。
なので、不要なものは、リサイクルショップに持っていく・必要な人に譲るなどの自分が納得いく方法で、ものに対する「もったいない」を変換し、不要なものを手放していくことができました。
2:「自分は片付けられない人間だ」とあきらめない
実家がゴミ屋敷だったこともあり、小学3年生の頃から「片付けたい」と思い続け、何度も片付けてみましたが、「片付けられた!」というような実感はほとんどありませんでした。そのまま、20歳で実家を出てひとり暮らしを始め、今度こそは片付けようと思っても、やはり片付けられない。
そうするうちに、だんだんと「私は片付けられないのでは?」というあきらめの気持ちに。「片付いていない家にいるのがいやだから休日は外に出かける」「片付いていない引き出しの中は見て見ぬふり」といった、片付けることから逃げるような行動をとるようになっていました。
しかし、しばらくすると「やっぱり片付けたいな」「片付いていない家はいやだな」という気持ちに。逃げていても悩みは解決しないと気がつきました。片付いていない家がいやだったら、片付けを進めるしかない。あきらめの気持ちは手放しました。
「実家がゴミ屋敷だったから私は片付けられない」と落ち込んだら、「あの頃に戻りたくない気持ちがあるから、片付けられる」と考えを上書きし、片付けが進んでいきました。