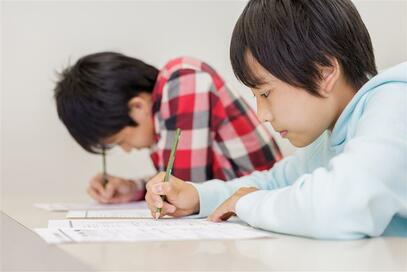地震や水害など、突然の災害に見舞われたとき、家族と連絡が取れない不安ははかりしれません。そんなときこそ、事前に「連絡ルール」を決めておくことが、冷静な行動につながります。今回は、国際災害レスキューナースの辻直美さんに、家族の安否確認をスムーズに行うための具体的な方法や、災害時に役立つ連絡手段について教えてもらいました。
すべての画像を見る(全2枚)連絡を取り合うルールがあると落ち着いて行動できる
「地震や水害などの災害にあったとき、家族とどう連絡を取り合うのか、安否確認をどうするのか、あらかじめルールを決めておくことはとても大切です」と辻さん。
辻家では、発災してから15分以内に連絡をし、つながらない場合、以降は30分後、1時間後、1時間半後、3時間後にかけると決めているそう。スマホの充電をなるべく減らさないためと、気持ちが焦るのを防ぐためだとか。
「災害用伝言ダイヤルのほか、実家や親せき宅など、被災地以外の人を中継地点にした『三角連絡法』も有効です。重要なのは、連絡方法の確認だけでなく、その優先順位を家族で共有しておくこと」(辻さん、以下同じ)
連絡が取れず、安否確認ができないうちは、心配で何度もかけ直したくなってしまうもの。でも結果、スマホの充電が切れてしまったら、連絡を取る術を完全に失ってしまいます。
「被災時の混乱のなかでも、やるべきことが明確だと、比較的落ちついて行動できます。そのためにもルールを決めておきましょう」
●連絡の取り方4選
1:発災後、15分以内に一度連絡を取る
2:そこから連絡が取れるまで30分後、1時間後、2時間後、3時間後と連絡を入れるタイミングを決めておく(焦らない・バッテリー維持のため)
3:災害用伝言ダイヤル(171)を使用する
4:被災地から離れている実家や親せき宅を連絡先にして伝言をお願いする(三角連絡法)
●災害用伝言ダイヤルの使い方
1:171にTEL
2:ガイダンスに従い、録音の場合は1を、再生の場合は2を入力
3:ガイダンスに従って、連絡を取りたい人の電話番号を入力
4:伝言を録音・再生する
頭で理解していても、被災時はパニックになるもの。NTTでは災害伝言ダイヤルの体験利用日を設定しています(毎月1・15日や防災週間など)。家族で練習をしておきましょう。
被災地以外に住む人を中継地点にした「三角連絡法」
被災地域から外へは比較的連絡が取りやすい傾向があります。遠方の親せきや知人に、それぞれが伝言を残し、連絡を取り合うことで、スムーズに無事を確認できます。
いざというとき用の連絡先リストをつくっておこう
連絡先はすべてスマホのなか、という人も多いはず。でも、それではスマホの電池が切れたら、だれともつながれない事態に陥ってしまいます。
いざというときの連絡先だけは紙にまとめて、家族で共有を。「水に濡れても大丈夫なようにラミネート加工して、冷蔵庫などに貼るのがおすすめ。被災時はアナログスタイルが強みを発揮します」
●書いておく人などの例
・同居家族全員
・避難させてくれる親せきや友人
・実家
・家族と自分の勤務先
・地域の防災担当
・地区班長
・民生委員
・近所の頼れる人
・PTA会長
・町内会長ケアマネジャー
・ヘルパー
・子どもの学校
・かかりつけ医院
・子どもの塾
・かかりつけ動物病院