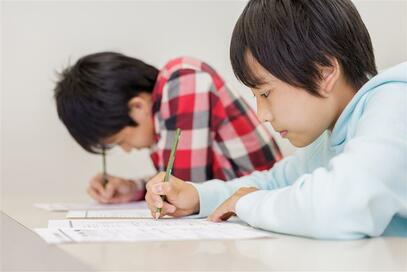通勤や子どもの送り迎えに自転車を利用している方は多いのではないでしょうか。自転車も来年4月には、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告する「青切符」制度が導入される予定です。安全な走行のためには、正しいルールを知っておくことが重要です。そこで今回は警察庁交通局交通企画課 理事官・須永敦雄さん(取材当時)に、自転車のルールについて教えてもらいました。
すべての画像を見る(全5枚)自転車は「車両」である
自動車とは異なり、運転免許が不要な自転車ですが、「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)」が罰則対象であるということを把握している方も多いと思います。けれど、正しい交通ルールに関しては知らないことも多いですよね。
「自転車は法律上、『軽車両』と位置づけられ、自動車と同じ『車両』の一種です。また、自転車の運転には守るべきもっとも基本的な『自転車安全利用五則』というルールがあります。運転する際は、これらの規則を遵守することが重要です」(須永敦雄さん、以下同)
<自転車安全利用五則>
1:車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3:夜間はライトを点灯
4:飲酒運転は禁止
5:ヘルメットを着用
自転車は車両であるため、原則車道を走行しなければいけません。ただし、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または一定の障害をもつ人の場合、車道または交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合は、歩道を通行できます。
「さらにいうと、自転車が車道通行するときは、『道路の中央から左側の部分の左端』に寄って通行。通行可能な歩道では相互通行ができますが、中央から車道より部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけません」
●自転車同士ですれ違う場合は「自転車を右に」が鉄則
また、自転車同士ですれ違う場合にも意識すべきことがあります。
「自転車同士がすれ違う際は、相手の自転車を右に見ながら、安全な間隔を保ってすれ違うようにしましょう。これは自動車と同様のルール。意外と知られていないので、ぜひ覚えたうえで、自転車を運転してほしいですね」
歩道を走る際は「徐行運転」が基本。徐行運転とは、「すぐに止まれる速さ」を定義します。歩道はあくまでも歩行者のための空間なので、自転車は普通の速度で走行してはいけません。
「ただし、歩道の中で自転車の通行指定がある部分では、歩行者がいなければ、状況に応じた安全な速度で走っていいですよ」
自転車レーンにも種類がある!
じつは、自転車レーンにはいくつかの種類があります。
「自転車レーンは3種類あります。いちばん安全に走ることができるのは『自転車道(自転車専用道)』と呼ばれるもの。ここは基本的には自転車での通行しか認められていません。ほかにも、『自転車専用通行帯』、『自転車ナビライン(自転車ナビマーク)』といったものがあります」
●3種類の違いと特長
<自転車道>
歩道や車道と完全に分離された自転車専用道路。これがある場合、原則として自転車道を通行する必要があります。縁石や柵などで区ぎられ、自動車の進入が禁止されているため、安全に走行できます。
<自転車専用通行帯>
道路標識で指定された自転車専用の車道で、線やマークで自動車と区別されています。自転車以外の車両の通行は原則できませんが、一部例外もあります。
<自転車ナビライン>
本来走行すべき「車道の左側」であることを視覚的に示す路面標示。青色の矢羽根型のマークや矢印、ピクトグラムなどで表示されていて、自転車以外の車両の通行も可能です。
「自転車ナビラインの矢印は、視覚的にわかりやすくしていることに加えて、逆走を防止する意味合いもあります。逆走は大変危険な行為であり、法律違反にも当たります。ぶつかりかけるなど、事故が起こりうるような事態が発生した場合は罰則の対象となる可能性もあります」
自転車道や自転車専用通行帯を正しく通行しないと罰則の対象となり得るので、正しく理解することが重要です。