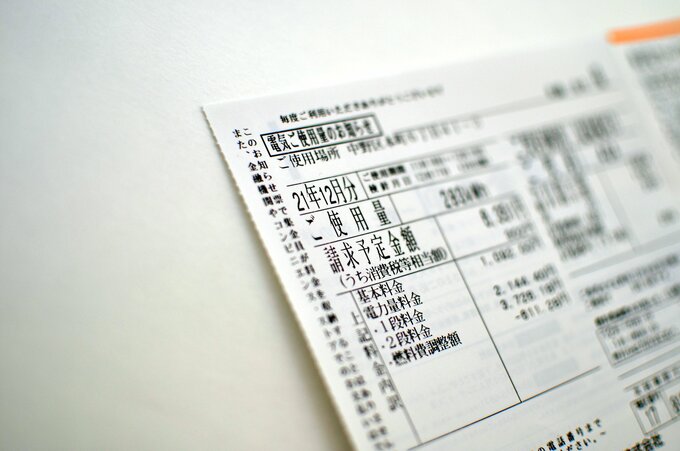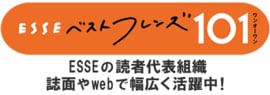寒い時季、1日じゅう暖房をつけている方も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが「電気料金」です。しかし、電気代はどのように決まっているのでしょうか…? 今回は電気にまつわる気になることを家電王こと、東京電力エナジーパートナー お客さま営業部の中村剛さんに教えてもらいました。
電気料金はどうやって決まるのか?
中村さんによると、毎月の電気料金は原則として、「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」で算出されているそうです。
この「基本料金」は、契約している電力容量(アンペア)やプランに基づいて計算されますが、「電力量料金」のなかには燃料価格の変動に応じて電気料金に反映をする調整費が含まれています。
じつは、この「燃料費調整額」がポイント。「サーチャージ料」のようなもので、燃料(石油、LNG、石炭など)の価格が上昇すれば調整費も上がり、その逆も同様です。電気代の変動が都度変わるため、この「値上がり」に対しては、電力会社ではコントロールできないのだそうです。
つまり、電気代を節約するためには、「使用する電力量を抑えること」や「適切な容量で契約すること」がポイントになります。
安易な電気代の節約方法はヒートショックにつながる恐れも?
しかし、冬の節電というと「暖房をつけるのを少し我慢する」「厚着をして過ごす」などを想像していませんか? このように“電力消費量を減らすこと”を目的とした節電には、危険が潜んでいる可能性があると中村さんは言います。
「この節約法は消費電力量を抑えることができますが、場合によっては家族のだれかに我慢を強いる可能性や“快適性”を犠牲にする恐れがあります。とくに冬の場合、家の中で極端な室温の差が生じると、ヒートショックによる死亡事故にもつながりかねません。
電気代を節約するうえで大事なのは、住んでいる人たち『全員が無理をしない』こと。だから、本来のエネルギー効用を損なうことなく、より効率的に使用する『省エネ』という考え方で節電しましょう。家の中の温度を効率よく一定の温度に保つことが、本当の意味での省エネや節約になりますよ」(中村さん、以下同)