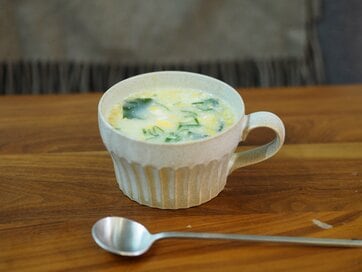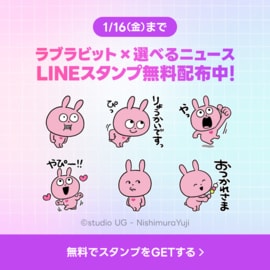何度片づけてもすぐリバウンド…そんな「片付かない家」には、共通する“落とし穴”があります。「収納を、動線・高さ・余白の3つの視点から見直すと、不思議なくらい部屋がスッキリします」と話すのは、ESSEフレンズエディターで住宅デザイナーの御園生梓さん。それぞれの視点からの、収納の見直しポイントを具体的に教えてもらいました。
すべての画像を見る(全5枚)1:収納の「動線」は“最短距離・最小アクション”に
ものをしまうとき、「わざわざ2階に上がる」「かがまないと届かない」「扉や引き出しを何枚も開ける」…。そんな収納は、片付けのハードルを上げる原因になってしまいます。
本来、収納は“動作の短さ”が命。たとえば、脱いだ上着は玄関からリビングに行く途中でサッとかけられる場所がベスト。洗面所のタオルも、ダイニングテーブルで使うペンも1歩も動かず取り出せる位置が理想です。
収納が“生活の流れ”に逆らっていると、自然と散らかります。収納場所は「動線の途中」に、「ワンアクション」で届くことを基準に見直すようにしています。
2:収納の「高さ」は家族の身長に合わせる
高すぎるつり戸棚や、奥行きのある棚の上段…。その“高さ”のミスマッチが、日常の散らかりの原因になることも。
日常でよく使うものは目線から腰までの「ゴールデンゾーン」の高さに収納しています。とくに子ども用品は、子どもの手が届く範囲に置くことで自分で戻す習慣が自然と身につきます。
また、大人でも取り出しにくい場所は「使わなくなる」「つい置きっぱなしにする」原因に。
収納の高さは、しまう人に合わせたカスタマイズが鉄則。今一度、家族全員の目線や動きを思い出して、使いにくい場所を見直すのはおすすめです。