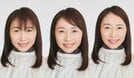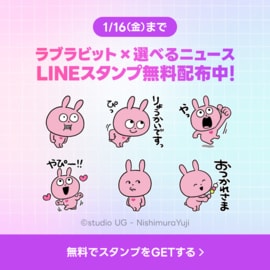管理や置き場所に困る、子どもの「学用品置き場」の便利な工夫をご紹介します。教えてくれたのは、小学2年生の長男と2歳の二男を育てながらシンプルな暮らしを実践している、あさこさん。ここでは、あさこさんが実践している、子どもが自分で支度や片付けをすることができ、忘れ物のチェックもしやすい学用品置き場をつくる3つのコツをお聞きしました。
すべての画像を見る(全5枚)1:学用品置き場は「キッチンの近く」にする
最初に意識したのは「場所選び」です。ランドセル置き場といえば、子ども部屋に置くイメージもありますが、わが家はキッチンのすぐそばに学用品置き場をつくりました。
理由はシンプル。「水筒や給食用のカトラリーを出し忘れにくいから」です。
子どもが帰宅したら、水筒や給食セットを取り出してすぐに流しへ。2歳の次男は自分ではまだ出すのが難しいので私が対応しているのですが、「キッチン近く」はとても使い勝手がよいです。
朝も「キッチンで準備してすぐにカバンにしまえる」のでかなり動線がいいと感じています。「子どもがやりやすい」だけでなく「親も気づきやすい」場所にすることで、忘れ物防止にもつながっています。
2:子どもが片づけやすい高さに設置
次に工夫したのは「高さ」です。
小学生になれば自分で準備や片付けもできるようになります。「子どもにやってほしい」と思うなら、物理的に「できる高さ」を用意することが大切だと実感しました。
現在は、床から38cmほどの高さの棚に、長男のランドセル置き場や教材を設定。毎日、学校から帰宅したらここにしまうようにしています。勉強をするのはダイニングですが、この収納はダイニングからも近い場所なので、距離的にもしまいやすいです。
小学生でも片付けやすい「動線」と「高さ」を意識することで、片付けのリズムがつくように感じています。