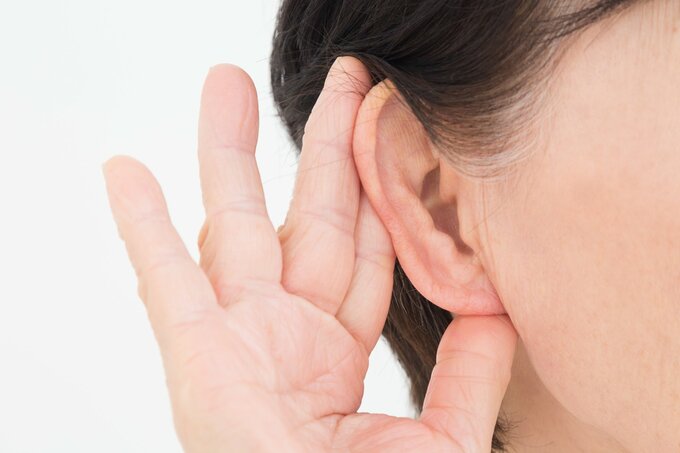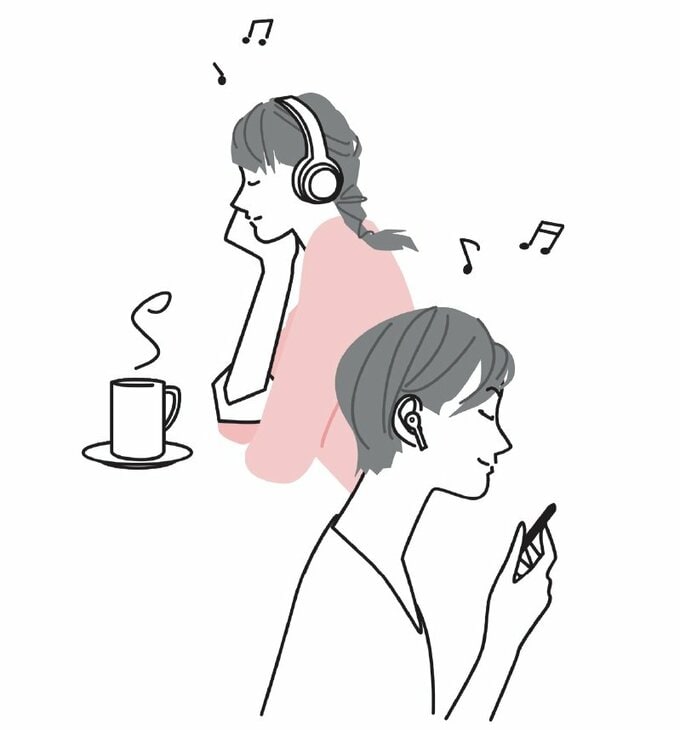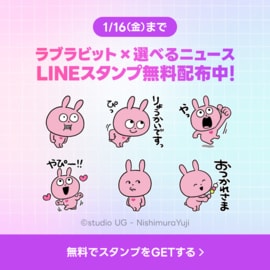自覚しにくく誰でもなりうる加齢性難聴
すべての画像を見る(全5枚)加齢性難聴の原因は内耳の中の有毛細胞(音を電気信号に変えて脳に伝える)の損傷。加齢や大音量を長時間聞き続けることで進行し、一度ダメージを受けた細胞は修復されません。
高い音や子音から聞き取りにくくなるのが特徴で、電子レンジや体温計の信号音に気づかない、「基地」と「位置」の聞き違いなどが生じます。血流の悪化もリスクとなり、動脈硬化のある人は高音域の聴力が低下しやすいとの研究結果が出ています。早く気づくためにも、ほかの病気(突発性難聴、メニエール病など)との鑑別のためにも定期的に聴力検査を受けましょう。
●難聴対策の基本は生活習慣。補聴器の使用は早めに
大きな音に長時間にさらされないことや血流の悪化を防ぐことは難聴の予防や進行を抑える効果があります。生活習慣の見直しは難聴対策の基本。運動習慣のある人はない人に比べて難聴になりにくいともいわれています。
聞こえの悪さを自覚したり周囲から指摘されたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。自分に合った補聴器を積極的に使うことは、社会活動や生活の質の維持、ひいては認知症予防に有効です。
●イヤホン・ヘッドホンの長時間使用に注意。増えている“騒音性難聴”
「2016~20年の20代女性の聴力は、2000~04年の40代女性と同程度」という衝撃的な報告が出ました。国立病院機構東京医療センターによると、近年、40代以下の男女ともに、音響によるダメージを最も受けやすい高音域(4000Hz)の聴力が明らかに低下しており、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く環境が影響している可能性が高いとのこと。
加齢と大音量が重なると難聴は加速します。音量を小さめにする、長時間聞き続けないなどの注意は全世代の現代人に必要です。