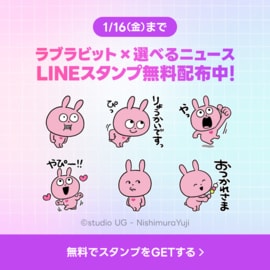ニュースなどで頻繁に聞く「金利の上昇」という言葉。住宅ローンを変動金利で組んだ家庭にとって、その影響は毎月の返済額に直結し、家計を圧迫する可能性があります。この状況に直面したのが、元銀行員でFP2級の資格を持つESSEonlineライター・谷ノ内真帆子さん。育休中で収入が限られるなか、冷静に準備を進め、金利負担を軽減するための行動に移しました。今回はそのときの経験をご紹介します。
金利がアップし状況が一変!わが家にピンチが…
わが家は2023年に変動金利で住宅ローンを組みました。最初は「低金利でラッキー!」と喜んでいたものの、2025年に入り状況は一変。1月に0.15%アップ、さらに7月に0.25%アップと、半年のうちに合計0.4%もの金利上昇が告げられました。
最初に通知を見たときは、正直「え? こんなに!」と驚きました。育休中で収入が少なく、双子育児で日々の出費も増えている状況のなか、この負担増は家計に大きく響きます。毎月の返済額も数千円から1万円ほど増える計算で、気持ちがどんより落ち込みました。
「このまま払っていけるのか…?」と不安を感じ、夜もよく眠れない日々が続きました。夫と話し合いを重ねた結果、「なんとかできる方法を見つけよう」と協力して取り組むことに。家計のやりくりだけでなく、金利の見直しを相談するため、銀行に交渉してみることになりました。
他行の借り換えも視野に。交渉準備を徹底した
金利上昇の通知を受けてから、すぐに対策を講じ始めました。まずは他行で借り換えをした場合のシミュレーションを行うことからスタート。インターネットや銀行窓口で金利や手数料を調べ、以下の3点のポイントをまとめました。
・借り換え後の適用金利の予想
・手数料や保証料、登記費用などの諸費用の総額
・総返済額の差額比較
これらをExcelで表にまとめつつ、シミュレーション結果をPDF化して銀行担当者に提示できるように準備をしました。具体的なデータを示すことで、交渉を有利に進める土台を固める狙いです。
さらに、借り換えにかかる時間や手間についても事前に整理しました。書類の準備や金融機関とのやりとりなど、生活とのバランスを考えて、現実的な手段であるかどうかを見極めることも大切です。
これらの準備をもとに、夫ともじっくり相談。借り換えに踏みきるかべきかを冷静に判断できる材料をそろえた状態で、銀行と向き合うことにしました。
銀行からの提案は…
いよいよ交渉に挑み、担当者に電話やメールで相談しました。すると、驚いたことに、担当者からは思いのほか前向きな返事が返ってきました。
「すべて0.4%アップのままというわけではなく、積立投信契約を条件に、上げ幅を0.3%まで抑えることができます」という案。条件つきとはいえ、当初の通知よりも0.1%低い金利ですむことにホッとしました。
積立投信はリスクを伴う金融商品ではありますが、家計にも無理のない範囲で設定し、毎月一定額を積み立てることに。条件内容をしっかり確認したうえで、契約を進めるとともに、大きなリスクを取らない運用を心がけました。
交渉の際に、事前に準備した他行の借り換えシミュレーション結果を示し、「借り換え検討している」と伝えたことも銀行側に譲歩の余地を生じさせた要因だと思います。