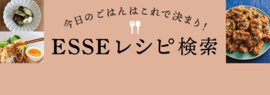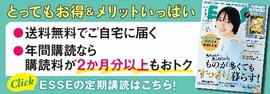●介護は大変だったけど、気づきもあった
――介護に対して明るくお話されていますが、当時は寂しさとかはなかったのでしょうか?
すべての画像を見る(全5枚)阿川:初期の頃には、このまま分かんなくなっちゃうのか、前の母には戻らないのかという、別人格になっちゃうようなショックは確かにありましたね。爆発して母を叱りつけて、母が泣き出すみたいなこともあったし。
母もまだ半分、しっかりしてる頃は、なんでこんなに家族に怒られなきゃいけないんだろうって、珍しく機嫌が悪くなったりしてましたね。算数テストとか脳トレゲームとかやらせると、それはできるし、しりとりなんか途中で「つまんないわね」みたいな。いろいろ初期の頃の方がぶつかることが多かったです。
そういう時期もあったんだけど、あるときお医者さまに、「今の医学では元に戻すことはできない」。そう言われたときに、「あ、昔の母を求めるより、今の母と毎日笑える日々を続けることの方が大事なんじゃないかな」って思ったのね。
母のひげが生えてきたり、爪が伸びたりするの見ていると、生きてるな、この人、って。ちゃんと体を循環させて毎日毎日コツコツ生きてるじゃない、この生物は、って。生きてるときを大事にしなくてどうするの? って思いましたね。
――そこから意識を変えられたのでしょうか?
阿川:諦観っていうのともちょっと違って、おもしろかったですよ。医学的に見れば確かに認知症で脳が衰えてるっていう現象が起こっているのに、なぜこういうことにはすばやく気がつくの? っていうこととか、ひょんなことをちゃんと覚えてたりしてね。
たとえば、母を助手席に乗せて父の病院に行くときに、窓を見ていて、「高いビルね」とか言って、数え始めたりして。「○○歯科」なんて看板が目に入ると、「小学校の友達に○○さんって人がいたのよ」って延々話すの。そこをまた通ると、「あら、小学校の友達に…」って、それ、先週も聞きました、みたいな(笑)。なにが始まるか分からない。
この人の脳みそはなにを感じてどう反応して、どこがクリアでどこがダメなのか、一概には言えないっていう。おもしろいな人間の脳は、って思うことが多かったですね。
――お母さまの介護は何年くらいされたのでしょうか?
阿川:認知症と診断されてからは9年半くらいですかね。仕事が忙しく、父と母の介護が重なった頃はちょっと大変でした。
覚えているのが、仕事をしてこれから横浜の実家に帰って晩御飯をつくらなきゃいけないってことで、おでんだったら便利じゃないですか。そうだ、おでんいいねって、おでんの種を持って帰ってつくったの。
そしたら、まず父の第一声、「おでんはあんまり好きじゃない」。第二声は、兄弟から。母が心臓の手術をしたあとだったので、「練り物は塩気が多いから、心臓にはよくない」だって。「必死で買ってきてつくったのに! ガーン!」ってイラっとしましたね。本にはリモートのお葬式の話も書きましたけど、兄弟とも見解の相違はいろいろありました。