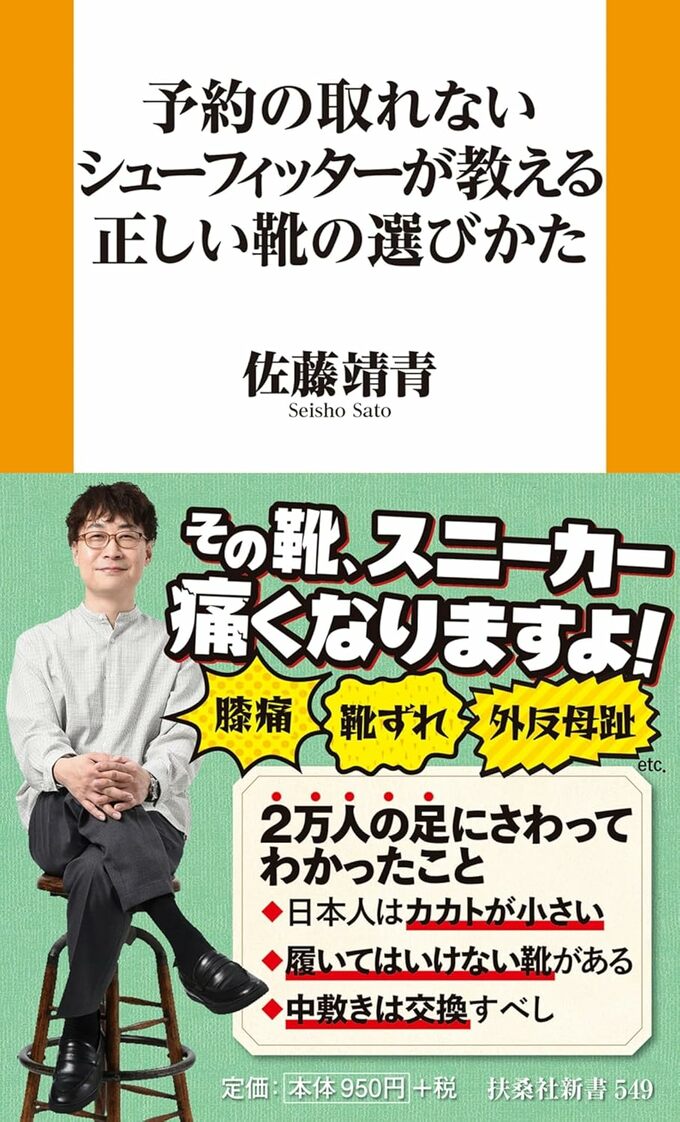鉄則その2:靴のサイズはあってないようなもの
すべての画像を見る(全3枚)「靴のサイズは何cmですか?」と聞かれて、即答できる方は要注意です。自分のサイズ感を過信するあまり、ネットで買うとかなりの確率でハズレを引きます。
●メーカーのサイズ表記は過信しない
私のもとにも、「ネットで買った靴が合わない」という相談は、非常に多く寄せられます。10年間、靴のサンプルをつくってきたので、よくわかるのですが、メーカーは靴をつくるときにサイズをはかっていません。26cmの靴はメジャーで測っても26cmではなく、「26cmくらいだから26cmにしよう」と、かなり適当に決めています。
JIS(日本産業規格)という規格はありますが、革靴時代の名残のようなもの。そもそも革とスニーカーのメッシュ素材では伸び具合が異なるうえに、日本の規格なので、海外メーカーには通用しません。「ざっくり換算すると3E(足囲のサイズ)くらいかな?」といった程度の目安にすぎません。別に手抜きではなく、サイズ表記はあくまで目安。最後は自分の感覚で決めてねというのがメーカーの基本的な考え方なのです。
●足のサイズを測るうえで重要なこと
オーダーメイドではなく、万人に売るわけですから、サイズは目安としてつけざるを得ない。同じ足でも革靴とスニーカーでは、1cm、人によっては2cmくらい違うこともあります。革靴が足のサイズを目安にしているのに対し、スニーカーは靴全体のサイズを基準にしているのでそもそもの前提も異なります。文句は、革靴とスニーカーが分かれた100年前の先人に言ってください。
「なら、店で測ってもらえばいいのでは?」と思う方も多いでしょう。たしかに今は店でAI搭載の最新機器によって、無料で足のサイズを測定してくれますが、その考えかたも甘い。
どんな高級マシーンでもはかるのは、じっと止まった状態の足です。止まっている足のサイズと、動いている足のサイズは、当然のことながらまったく異なります。もちろん、重要なのは動いている足のサイズです。
だから、靴をはいて店のなかを歩き回るという原始的な試し履きにはかなわないのです。自分の足のセンサーを信じるしかありません。
鉄則その3:インソールは取り換える
ひざや腰など、30歳を超えるとどこかに痛みが出てきます。私も若いころのケガの後遺症で膝痛とは数十年のつき合いです。これを靴単体だけで解決することは難しいのですが、ラクにする方法はあります。
●中敷きは「機能性インソール」に
既存の中敷きを機能性インソールに交換するという手段です。インソールは中敷きとも言われますが、ひと昔前は、ゆるい靴をフィットさせるための調整に利用されるものでした。これはこれで問題があるのですが、それはさておき、今は用途が異なります。
現在、インソールは靴の機能を向上させるためのパーツとして販売されています。
昭和から平成にかけて、大人といえば革靴が主流でした。しかし令和になって、ビジネスカジュアルが広まったこともあり、機能性スポーツシューズやスニーカーでも通勤可能という職場が増えています。これらの靴は基本的に、もともとついている中敷きを抜くことができます。なぜ抜けるのかというと、設計の立場から言えば、各自でカスタムしてほしいからです。
しかし、このメッセージは販売の現場には届きません。新品の靴の中敷きを交換するなど、客に余計な出費を強いるだけだからです。
●靴選びは「目的×サイズ×インソール」の掛け算で考える
ここで冷静に考えてほしいのですが、靴という入れ物にはこだわるのに、足が直接触れる中敷きをないがしろにするのは、愚の骨頂です。私は、お客様と一緒に靴を選ぶというアテンドの仕事もしていますが、2万円の靴よりも1万円の靴に5000円の機能性インソールを組み合わせるほうがはるかに効果的ということは身をもって実感しています。
靴を新調する前に、中敷きを適正な機能性インソールに取り換えただけであっさりとひざの痛みが解決したことすらあります。
ひざ、腰の痛みのほとんどは姿勢の悪さに起因します。姿勢を正すには靴単体より、機能性インソールを使ったアプローチのほうが効果は数倍あります。今の時代、靴と機能性インソールは、セットだと思ってください。
ひざも関節も消耗品です。減りはしても増えることはありません。歩きやすい靴が欲しいと思ったときに、まず見るべきは値段でもブランドでもありません。靴には進むためか止まるためかといった目的があり、それを見誤ると高価な靴でも足に負担がかかります。
さらに、サイズ表示は目安にすぎず、自分の足と靴の相性を知るには実際に歩いて確かめるしかありません。そして、機能性インソールを一緒に購入すること。この工程こそ、靴の性能を引き出し、姿勢や痛みを改善する最短ルートなのです。
靴選びは「目的×サイズ×インソール」の掛け算で考える必要があるのです。