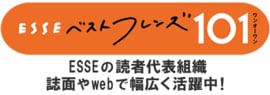今年9月、自身の名前を冠した新店「三國」をオープンし、71歳にして新たな挑戦を始めたフランス料理の巨匠・三國清三さん。11月2日放送の『情熱大陸』に出演したシェフが、この新店舗でやりたいことは、グランメゾンを率いていたときにはできなかった、ひとりで料理に向き合うこと、そして、お客さんひとりひとりに向き合うことです。そこで今回は、料理人として新たな道を歩む覚悟を胸に、第2章をスタートさせた三國シェフの原点となる10代の経験や、スタッフ育成、そしてこれまでの軌跡をご紹介します。
※ この記事は『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(扶桑社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。
すべての画像を見る(全2枚)長く続けられたのは、大変だった「10代」があったから
スタッフの採用や教育もオーナーシェフの大きな仕事のひとつだ。
その店を5年、10年、15年と続けていくには、一緒に働くスタッフひとりひとりに成長してもらうしかないのである。だが、これは料理人に限らないが、身体で技術を覚えていかなくてはならない職種は、採用も教育も非常に難しくなってきているのが現状だ。
極端なことを言えば、僕らの時代は、10代の子なんて人間扱いされなかった。来る日も来る日も下働きの日々が続く。どうしてこんなことをやらなければいけないのかなんてことは、だれも説明してくれない。「やれ」と言われたことを一生懸命にやり続けるしかないのだ。
理不尽だと思うことは多々あったし、上下関係の中で人間の裏側も見た。見習い同士のケンカや小競り合いもずいぶん経験した。ただ松下幸之助さんもおっしゃっていたが、そんな10代の経験が人間としての基盤をつくる。
僕がこうしてオーナーシェフとして長くやってこられたのも、あの10代があったからだと断言できる。
「見て覚えろ」が当たり前だったあの頃…
僕の場合はどこへ行っても「見て覚えろ」だった。手取り足取り教えてもらった記憶はない。
仕事中に見たこと聞いたこと感じ取ったことを、だれもいなくなった厨房で再現してみる、練習をくり返す。そうやって技を身につけていった。
札幌グランドホテルでは社員寮に入っていたにもかかわらず、寮にはほとんど帰らなかった。厨房に泊まり込んでその日に覚えたことを練習していたのだ。タオルを卵に見立ててフライパンに入れ、オムレツを焼く練習をくり返したことも、今では懐かしい思い出だ。
とはいえ、今の時代に「見て覚えろ」方式が通用するとはとうてい思えない。さまざまな分野で職人さんがどんどん減ってしまい、後継者不足が騒がれているが、料理人だって例外ではない。やはり、ある程度までは教えて、技術の習得を助けることも必要なのではないか。
それに、そもそもなりたがる子が少ないのだから、その数少ない子たちを一人前に育てていけるかどうかは店にとって死活問題である。料理人だけでなくソムリエでもサービスマンでも同様で、きっちり教育していくことが必要だと僕は思う。