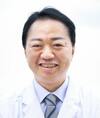秋バテを助長するNG行動と対応策
すべての画像を見る(全5枚)秋バテは次のような行動で助長する恐れがあります。日々の生活で意識して、対応策をとりましょう。
●NG行動1:朝起きるのが遅いなど生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れは秋バテを助長します。とくに朝遅くまで寝ているのはNG。
朝日を浴びることで、幸せホルモンであるセロトニンが分泌されます。セロトニンは、日中元気に活動することを助けるほか、夕方以降は睡眠促進ホルモンであるメラトニンに変化します。これによって、よい睡眠が得られ、秋バテの原因となる自律神経の乱れを防げます。
●NG行動2:朝ごはんを食べない
朝ごはんを抜くことで、秋バテを助長することもあります。
朝ごはんを食べることは、水分・栄養補給になるだけでなく、おなかを刺激して自律神経を活発化させてくれ、秋バテに強い身体をつくります。
また、秋バテで疲れのたまった身体の回復に必要なビタミンやミネラルも補給してくれます。できるだけ食べるようにしましょう。
●NG行動3:湯船につからず、シャワーですませてしまう
忙しいなどで湯船を浸からずシャワーのみですませていると、秋バテを助長する恐れがあります。
体温より少し高めの38~40℃程度の湯船にゆっくりとつかることで、リラックス効果とエアコンで冷えた身体を温めてくれます。副交感神経を刺激して、全身の血流や胃腸の調子を整えてくれます。
入浴は入眠の2時間前を目安にすると深部体温をいったん上げられ、寝るまでに2時間かけて下げることで良好な入眠が得られます。
●NG行動4:冷たい飲み物ばかり飲む
まだ暑いからと、冷たい飲み物ばかりを飲んでいませんか? しかし、冷たい飲み物は胃腸に負担をかけ、身体を冷やしすぎてしまうこともあります。
代わりに白湯をとることで、身体を冷やさずに水分補給ができ、リラックス効果で副交感神経も刺激してくれます。
●NG行動5:甘いものやそうめんのような麺類ばかり食べる
スイーツやパン類、麺類などの炭水化物の多い食事は肝臓に負担をかけてしまい、バテた体の回復に必要な栄養素が十分にとれていないので、秋バテの一因になります。
秋バテになりにくい体をつくる栄養素3つ
秋バテを予防するのに効果的な3つの栄養素を紹介します。
●1:タウリン
多く含まれる食材:イカ、タコ、ホタテ、アサリ、サザエ、シジミ、カツオ、ブリなどの魚介類
タウリンは、体内のさまざまな代謝を助け、自律神経のバランスを保つ働きがある成分であるため、秋バテ対策にオススメです。肝臓や心臓の機能をサポートする働きにより、全身の“回復力”を底上げします。
水溶性なので、みそ汁やスープなどで日常的に取り入れるとよいでしょう。
●2:オメガ3脂肪酸
多く含まれる食材:サバ、イワシ、サンマ、アジ、マグロ、鮭、アマニ油、チアシード、エゴマ油など
オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、青魚に豊富に含まれる必須脂肪酸です。細胞の炎症を抑え、血流を改善し、脳と神経の働きを助けることで、自律神経の乱れや気分の落ちこみを和らげます。季節性の気分不調や睡眠リズムの乱れにもオススメです。
●3:鉄分
多く含まれる食材:レバー(鶏・豚)、赤身の牛肉、カツオ、マグロ、アサリ、シジミ、卵黄など
鉄分は、とくに身体に吸収されやすく効率よく鉄分を補える動物性の「ヘム鉄」は、血中の酸素運搬に重要です。不足すると倦怠感や立ちくらみ、冷え、集中力の低下、さらには気分の落ちこみにもつながるため、意識的に摂取すると秋バテ予防になります。
秋においしい魚介類を摂取するようにすることで、含まれているタウリンやオメガ3脂肪酸、鉄分などの栄養素の力を借りて、疲労回復や健康維持に役立てられます。
これから朝晩の気温差が大きくなりますので、秋バテにならないよう、しっかりケアして元気に秋の時間を過ごしましょう。