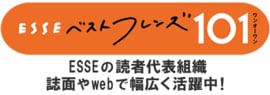福岡で飼い主が出会ったのは、ちょっと変わった風貌の保護猫・もんた。多くの不安を抱えながらも引き取って始まった暮らしは、自然豊かな糸島での散歩や、そっと寄り添う時間に満ちていたそう。ここでは、病気と懸命に戦ったもんたと飼い主の日々について紹介します。
※ この記事は『もんたのいた日常』(辰巳出版刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。
すべての画像を見る(全5枚)ありのままを発信する
もんたは最初から成長が遅くて病弱だった。食が細く、重い便秘を繰り返していた。
受診の結果、体が成長しない病気「小猫症」ということもわかった。原因不明の不調よりは、病気の正体がわかり、なにをすればいいかはっきりした方がいいと思う。
最初、SNSなどで病状を公表するのは迷いがあった。病気の動物の話題は深刻になりがちで、もんたを見て暗い気持ちが先行してしまう可能性があるからだ。でも、病状を知ったうえでしっかり向き合っているのがわかれば、ファンのみんなも安心だろう。だからありのままを伝えることにした。
すると、病気や対策についてもっと知りたいという要望もいただいた。なにかの役にたつかもしれないので、noteに現状と対策をまとめた記事を書いた。
2021年10月、強制給餌と釜めし
2021年10月14日、もんたを迎えてちょうど2年が経ったので、記念にもんた用の釜めしをつくった。お湯をはった釜の上にウェットフードを載せて、フタをして温めるという趣向だ。
この頃のもんたは毎回強制給餌をしなければならないほど食欲が落ちていた。食べないかもしれないと思いつつ、目の前に差し出してみる。しかし、予想に反して興味津々でしっかり食べてくれた。
強制給餌はお互いに負担が大きいので、「経鼻カテーテル」で鼻から管を通して栄養を与えることにした。カテーテル生活は強制給餌よりはラクだが、いつものフードより栄養価の低い液体しかあげられないので、相当な量をあげないといけないことになる。先の見えないトンネルにいるようだった。それから1か月以上経ち、自ら水を飲み始めたもんたを見たときは、やっと光が見えたようだった。