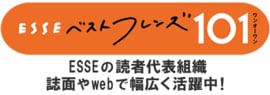試供品やいただきもの、買いすぎた日用品や食品、そして「もったいないから使えない」と思ってキープしてあるもの。家の中に「結局使わずに眠っているもの」はありませんか? 今回は、カナダ在住のブロガー筆子さん(60代)が実践している工夫をご紹介。ものを使いきることで、スッキリ気持ちよい暮らしが叶いますよ。
ものを「使いきる」ための5つのコツ
若い頃の私は、「取っておけばそのうち使うかもしれない」と、さまざまなものをしまい込んでいました。けれど、その「いつか」は来ませんでした。逆に、存在を忘れて使いそびれたり、劣化して結局使えなくなったりしました。
そんな経験から「取っておく」より「使いきる」方が、ずっと健全で気持ちがいいと感じるようになりました。ミニマリストになって、ものをため込むのをやめ、家の中も気分もすっきり。買い物の仕方や、ものとの向き合い方も変わりました。
今回はそんな使いきる暮らしを実現するために、私が実践している5つの工夫を紹介します。
1:使いきってから次を買う
死蔵品が生まれるいちばんの原因は買いすぎなので、やたらと買わないようにしています。とくに使いきっていないものがあるのに、新しいものを買うことはありません。これは、節約のためというより、ものを増やさないための予防策です。
洗剤や文房具、化粧品、ストック食品など、「必ず使う」と思う日用品ほど油断すると在庫が増えます。
日用品の買い物はアマゾンの定期購入を利用しているため、実際にはトイレットペーパーを1ロールだけ買うことはありません。しかし、ひとつのロールを使いきるまで何日かかるかを調べ、その結果をもとに次の購入日を決めています。
ストック品を使うペースを把握しておくと、買いすぎることはありません。
2:使いたいものは、手に取りやすい場所に出しておく
死蔵品は収納の奥にしまわれていることが多く、その存在をしばしば忘れがちです。使いきりたいものは手に取りやすいよう、目につきやすい場所に置いておきます。
たとえば、私は先日まで数年前の確定申告のためにとってあった紙の裏をメモに使っていましたが、まず紙を保管していたホルダーを箱から出し、使える裏紙をすべてホルダーから外して、引き出しのいちばん上に入れておきました。
ほかにも、たまっている化粧品のサンプルは、トレーにまとめて洗面所に置く、乾物を使いきりたいときはキッチンの目立つ棚に出す、といった工夫ができるでしょう。
視界に入れば、自然と手が伸びます。逆に見えないところにあるものは、もっていないのと同じことです。「気づいたら期限ぎれ」にならないよう、見える化を意識してください。