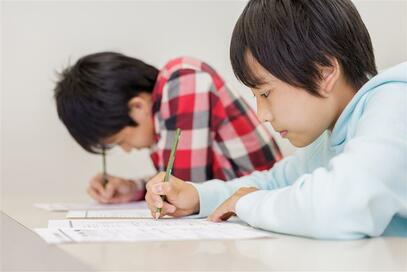2024年11月に自転車に関するルールが改正された道路交通法が施行されました。2026年4月には、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告する「青切符」制度が導入される予定です。そこで今回は警察庁交通局交通企画課 理事官・須永敦雄さん(取材当時)に、正しい自転車のルールについて教えてもらいました。
自転車運転で罰則対象になったことは?
昨年改正された道路交通法(道交法)ではおもに、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)」の2つが強化されました。
●運転中にながらスマホをした場合
<対象>
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為
<罰則>
・違反者に6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
「“交通の危険を生じさせた場合”とは、運転中のながらスマホが原因で交通事故を起こした場合や、事故には至らなくても車や歩行者の進行を妨げた場合などが該当します」(須永敦雄さん、以下同)
●酒気帯び運転及び幇助の場合
<対象>
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車を提供した人
<罰則>
・違反者に3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・自転車の提供者に、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・酒類の提供者、自転車の同乗者に2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
「じつは自転車での飲酒運転事故は原付や自動車に比べて深刻化することが多いんです。また、お酒を飲んでいることを把握しているのにも関わらず、自転車・お酒を提供した場合も罰則対象。ひとりひとりの意識が大切です」
イヤホンをつけての運転はOK?NG?
罰則の基準が分かったところで、気になるのは処罰の対象となる具体的なラインです。まず、「イヤホン(有線・無線に関わらず)」をつけた運転。街中でもよく見かける光景ですが、「運転中のながらスマホ」に該当するのでしょうか?
「今回の罰則対象は“手に持つ”という点がポイントなので、イヤホンでの通話や音楽鑑賞など、ハンズフリーの状態での運転は、画面を注視していなければ、ただちに道交法違反には当たりません。ただし、これはイヤホンをつけての運転が全面的に認められているという意味ではありません」
須永さんによると、イヤホンをつけて運転すること自体に罰則はありませんが、都道府県公安委員会の規則で、イヤホンをつけ「周囲の音が聞こえない状態」での運転は禁止されています。
「大切なのは、周囲の音が聞こえるかどうかです。周囲の音が聞こえないと、救急車の接近や、うしろからの警笛に気づくことができませんよね。そのような危険を察知できない可能性がある場合は、走行を禁止されているので絶対にやめましょう」
●警察官に声をかけられてもあわてない
イヤホンで音楽を聞きながら自転車を運転していると警察官に声をかけられこともあります。しかし、その際に大切なのは、なにか違反をしたと思って“あわてない”ことです。
「パッと見だけではイヤホンなのか、補聴器なのかわかりませんよね。なので、禁止事項に該当しないか、『確認』の意味でお声がけさせていただく場合があります。そのときに“止まれるのか?”というのは1つの判断基準になることがあります」
声が聞こえれば当然停車できますが、聞こえない場合は停車できません。警察官に声をかけられた=罰則対象、というわけではないので、落ち着いて対応しましょう。