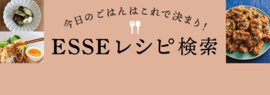2014年『ビオレタ』で第4回ポプラ社小説新人賞を受賞しデビューして以来、『夜が暗いとは限らない』、『水を縫う』など、数々の話題作を世に生み出してきた、小説家・寺地はるなさん。
小説家・寺地はるなさん『わたしたちに翼はいらない』インタビュー
すべての画像を見る(全4枚)8月18日に発売した、『わたしたちに翼はいらない』(新潮社刊)は、寺地さん自身が「これほど精神的肉体的に消耗する連載は初めてで、悩みまくりながら書いた、私にとって大事な作品」と語るほど、全力を注いだ作品です。そこで今回は、寺地さんに本作にまつわる話を伺いました。
●いろんな人に自分事として読んで欲しかった
『わたしたちに翼はいらない』は、生まれ育った地方都市で暮らす4歳の娘を育てるシングルマザーの朱音、朱音と同じ保育園に娘を預ける専業主婦・莉子、マンション管理会社勤務の独身・園田の3人を軸に展開する「心の傷が生んだサスペンス」です。しかし、元々の作品には“園田”という人物は存在していなかったのだとか。
「2019年に莉子と朱音を書いた短編があるのですが、編集担当の方がその短編を気に入ってくださったので、この前の連作短編の『希望のゆくえ』(新潮社刊)には入れませんでした。それを大幅改変して長編を書こう! となったのがこの作品のきっかけです。
でも、対照的な女性2人の主人公となると、女性が書いた女性の話で終わってしまう可能性があって…自分には関係ないと感じる人もいるかもしれない。できればいろんな人に自分事として読んでほしかったんです。だから、この2人とは違う属性で生きている人が必要で、そこに入れたのが園田でした」(寺地はるなさん、以下同)
3人の主人公たちには、原因や理由は異なりますが、“子どもの頃に負った心の傷を癒やせないまま大人になり、その呪縛から解放されていない”という共通点があります。
「性別が一緒で、子どもの人数が一緒だからと言って、私が莉子や朱音を理解できるかというとそんなわけでもないし、男性だから園田は私と違うというのでもない。莉子は、私と性格が全然違うタイプだなと思いながら書いてきたけど、それでも感情として理解できる場面はいろいろとあったし、だれかに特別共感できたというのはないかも…。全員が自分の一部であり、自分ではない。そんな感じですね」
主人公たちのだれにでも共感ができる…その言葉通り、性格や抱えている悩み自体に共感はできなくとも、心の中に芽生えた黒い感情や嫉妬、悩みなどは、自分にも思い当たるところがある、“他人事ではない”リアルさが本作には存在しています。