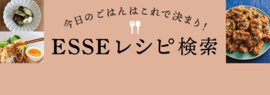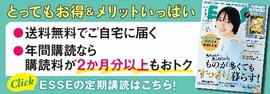宮沢賢治といえば、没後90年を迎えた今もなお多くのファンに愛される、岩手県花巻市が生んだ文豪のひとり。そんな賢治の代表作の数々を、擬人化した猫でコミカライズし続けているのが、漫画家のますむらひろしさんです。今年5月には、およそ40年前に漫画化を手がけた『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』『グスコーブドリの伝記』(ともに扶桑社刊)の3冊が文庫で復刻されました。猫たちが登場人物となり賢治の作品世界を演じる様子は、どこか懐かしくユーモラス。夏休みに子どもが名作文学に触れる入門編としてもぴったりです。
自身もこれまで30匹以上の猫と暮らし、現在も3匹を家族に迎えている愛猫家でもあるますむらさんに、なぜ賢治作品を猫で描き続けるのか、聞いてみました。
すべての画像を見る(全4枚)賢治の童話「猫の事務所」が創作の原点
――猫が登場人物の漫画をライフワークとして描き続けているますむらさん。もともと子どもの頃から猫はお好きだったんですか?
ますむら:子どもの頃から家で猫は飼っていたけれど、じつは好きというほどじゃなくて、むしろあまり興味がなかったんです。ただ、自分の中では猫といえば飼い猫じゃなくて野良猫というイメージがあって。同じ町には住んでいるけど、人間のつくった社会システムとはつかず離れず、勝手に生きている感じがいいなと漠然と思っていました。
――そんな猫が、ご自身の創作と結びついたのはなぜですか。
ますむら:転機になったのは、山形県米沢市から上京して、東京暮らしになじめずにいた20歳ぐらいの頃。テレビで水俣病の特集をやっていて、水銀で汚染された魚を猫に食わせて発病させる実験の映像を見て、人間の傲慢さにすごく怒りが湧いたんですよね。人間のつくり上げた文明の欺瞞(ぎまん)を考えるようになった。
ちょうど同じ頃、宮沢賢治の作品と出合ってその奥深さと不思議な世界にどんどんハマっていきました。作品から立ち上ってくる東北の空気に、同じルーツをもつ者として強烈にひかれたんでしょうね。そんな中、賢治の『猫の事務所』という童話に出てくるかま猫にシンパシーを抱いたんです。
――猫が主人公の賢治作品と、そこで出合うわけですか。
ますむら:事務所の先輩の三毛猫や虎猫から理不尽に虐げられるかま猫の悲しみが、東京になじめずに疎外感を味わっていた自分と重なった。さらにそこへ、水俣病の猫実験を見て感じた社会への怒りが重なったんだよね。それで、猫たちが人間を滅ぼしてしまおうと会議を開く『霧にむせぶ夜』という漫画を描いて、それがデビュー作になりました。
――なるほど、デビュー作ですでに「賢治」と「猫」という要素が、ますむらさんの中で繋がっていたんですね。