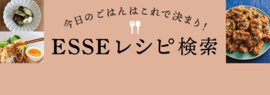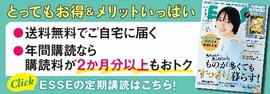●ぞうきん持参で早朝出勤し、営業職に
すべての画像を見る(全5枚)主婦時代、割に合わなくても時間をかけて丁寧に添削の仕事を仕上げていたことが、思わぬ幸運をもたらしてくれたのでしょう。
正社員として就職しても安心しないのが酒井さんです。「厳しい会社だから、使い物にならないとクビになる」と考え、子どもたちが寝ている早朝に家を出て、ぞうきん持参で始業2時間前に出勤。「19年間主婦をやっていたから、掃除くらいはできるだろう」と、オフィスの掃除を始めたのです。この朝の2時間が、今につながったと振り返ります。
「当時、私より早く出勤していた70代の先輩社員がいました。私は先輩の『一番乗り』を妨げまいと、二番目に出勤。掃除をしながら、先輩から、設立当時の話やお客様のことなど様々なことを学びました。加えてメールや手紙の整理をしたり電話を受けたりしていると、右も左も分からない新人でも、だんだんと取引先の名前を覚えるようになるんです」
その先輩も数年後には他界し、後を継ぐ形で営業職がスタート。ここでも、早朝出勤が思わぬ実りをもたらしたそうです。
「最初は新規営業で、名簿を見て電話をかけるだけ。でも、7時台に出勤すると、FAXの折り返し電話をしたら取引先の社長さんが出られて、お互いに名前を覚えて雑談も生まれてくる。営業は社長と話をして決める仕事。とくに企業によっては朝7時台に電話しないとつながらないところもあるので、朝に話ができることでお客さんとの縁がどんどんできていったんです」
“朝活”により営業出張も増え、仕事は好調。さらに、文学部出身で文章も書けた酒井さんは、勤務先が主催する文章のセミナー講師や社内新聞の編集なども任せてもらえるようになり、今では講師や営業の仕事で全国を飛び回ることも多いそう。
「最初のお給料は、アパートの家賃15万円を払える程度。児童扶養手当などの諸手当や養育費を合わせて、食べさせるのがやっとでした。それから15年間仕事を続けた今、給料は手取り24万円にアップ。なんとかがんばっていれば道は開けるんだ、と思いましたね」
今でも初心を忘れず始発出勤を続け、会社の掃除をしてから業務を始めるという酒井さん。「トイレ掃除をしていると、不思議と会社に愛着もわく」といいます。
「時々すごくつらいこともありますが、翌日早朝に出勤してトイレを磨いていると、『まあいいか』という気分になるんです。今では、皆さんが私にゴミの捨て方を聞いてくるようになりました(笑)」
●思春期真っ盛りの二人の子も、やがて自立
たくましく変化していったのは酒井さんだけではありません。二人の子もそれぞれ、自分の力で道を切り開いていったのです。
離婚当時、長男は高校生、長女は中学生。3人で家を出た日、3LDKの旧マンションから持ってきた荷物が小さなアパートに入りきれず、長男は引っ越し業者に「坊や、あのお母さんじゃ大変だから、あんたこれからがんばるんだよ」と言われたそう。
「その言葉通り、親は世間知らずの“ダメ母”で、お小遣いもロクにあげられなかったから、自分がしっかりするしかなかったのでしょう。息子は私立校の剣道部に所属していたんですが、他の学生が使い古した竹刀を継ぎ合わせて使ったりして、離婚後は一本も竹刀を買わずに乗りきりました。
じつは彼は、中学時代に、肩から下の筋肉が少なくなる筋ジストロフィーの診断を受けていました。そこで離婚後まもなく、障害年金を受給するために障碍者申請をしてもいいかと相談すると、『俺を売る気か!』と、手が上がらないのに私に殴りかかってきたんです。障碍者としてではなく、自分の力で道を切り開きたかったんですね。彼はその意志を貫き、部活で使う道具だけでなく、大学の学費から就職まで、ほとんど親の力も借りなかった。大学は奨学金制度を使い、就職も障碍者枠を使わず自力で金融機関に内定をもらいました。今では格安スマホの料金も自分で値下げ交渉するほど“締まり屋”に成長しています」
長男が就職して家を出てからは、酒井さんは住まいを縮小し、ラーメン屋の2階に転居。当時高校生だった長女はその住居を恥ずかしがっていましたが、長男と同様、自分で道を切り開いていきました。高校時代から飲食店でバイトをし、「接客業で就職する」と、バイトを続けながらホテルスクールに通いました。その後、大手外資系ホテルに就職して、独立。
「娘は独立して家を出ていく日に出会った引っ越し業者と電撃結婚しましたが、出産を経て、2年もしないうちに離婚。私が19年間も結婚生活を我慢して、離婚した直後に明るくなった姿を見てきたので、決断が早かったんです(笑)。今はシングルマザーとして奮闘しているようですが、ここでべったりと手助けをしたら彼女は自立しません。私は少し離れた場所で一人暮らしを謳歌しながら、見守ることにしました」