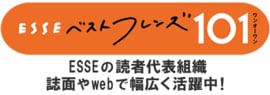「息ぎれ」や「動悸」、「不眠」も自律神経の乱れが影響
息切れや動悸も自律神経の乱れが大きく関係しています。自律神経は血管の拡張・収縮の働きにも深くかかわるので、心臓がドキドキすることも増えます。
さらに、これは睡眠の問題とも関連しています。更年期は仕事やプライベートでも責任が山積みになってくる時期。朝から晩までがんばりすぎてしまうため、本来、夜になるとリラックスを促す副交感神経にスイッチする自律神経が交感神経優位のままになり、ベッドに入っても心臓のドキドキがなかなか治まらず寝つけない…という話もよく聞きます。
すべての画像を見る(全5枚)たとえ横になってすぐ眠れたとしても、交感神経から副交感神経のきり替えがうまくいかなくて、睡眠中にホットフラッシュのようなことが起こり、中途覚醒や早朝覚醒することも増えます。眠りたいのに眠りが浅く、ぐっすり眠れない。若いときだったらスッと眠れた人も眠れなくなってきます。
更年期のこうした睡眠障害は、いわゆるうつ病の方の不眠とちょっと性質が違います。うつ病の人は、精神を安定化させるホルモン・セロトニンが不足するのが主な原因です。一方、更年期の不眠は、自律神経のきり替えがうまくいかず温度調整ができない機能的な面も大きいのです。
イライラ、憂うつも同時に起こりがち
さらに更年期は女性ホルモンの減少に伴い、セロトニンも減少するのでメンタル面でも不調が起こりやすく、どちらの要素も重なる形になります。このセロトニン不足は「くよくよしたり、憂うつになる」という症状とも関係します。
のぼせと冷えが表裏一体であるように、イライラと憂うつも同じように表裏一体で起こりやすいです。イライラすると、その後、落ち込みやすくなります。自律神経のきり替えがうまくできず、気温や環境、変化による刺激に弱くなり、心身が過剰に反応してしまうのも更年期のひとつの特徴といえます。
血流をよくするセルフケアを、生活に取り入れて
「頭痛やめまい」「疲れやすい」「肩こり、腰痛、手の痛みがある」といった症状は、更年期世代に関わらず年齢問わず起こりうる不調ですが、これらも血の巡りが大きく関係しています。
手っ取り早い改善法は、血流をよくする運動です。ヨガやウォーキング、ストレッチなどはおすすめです。
それと同じくらい大事にしてほしいのが、ワークライフバランスです。更年期はまさに「更新」、「新しく変化する」時期。がんばりすぎず、仕事も家事もペース配分を考えることが大切です。
※ 更年期の症状の感じ方、対処法は人それぞれ異なります。ご自身の体調に不安がある場合は、早めに医療機関を受診してください