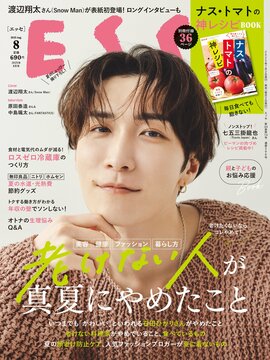スマホやタブレット、学習アプリなど、幼児期から子どもにデジタルツールに触れさせる機会が増えている昨今。親としてどのように関わらせるべきか迷っている人も多いのでは? そこで今回、心理学や脳科学などに詳しい「Five Keys」代表の井上顕滋さんに、デジタルツールの使用が脳の発達に及ぼす影響と、デジタルに頼りすぎないバランスのよい学習法について話を伺いました。
すべての画像を見る(全3枚)幼少期からのデジタルツール活用がもたらす影響
井上さんによると、子どもの脳は、経験によって神経回路がつくり変えられる「神経可塑性(しんけいかそせい)」が高いため、デジタルツールを適切に使うことで、脳の発達を促進することができる、と言います。
フロリダ国際大学のシェイル・F・グリフィス博士らによる研究(※1)でも、質の高い学習アプリによって、子どもの数学力や読み書き能力、語彙力が伸びると報告されているそう。
一方で、デジタルによる過度な刺激にはリスクも。
「バージニア大学のアンジェリン・S・リラード博士らによる60人の4歳児を対象とした研究(※2)では、9分間テンポの速い動画を見ると、子どもの注意力や問題解決能力といった実行機能が即座に低下することが示されました。脳の前頭前野(自己抑制や計画性を司る領域)は発達が遅いため、デジタル刺激にさらされすぎると、欲求を抑える力が育ちにくくなります」(井上さん、以下同じ)
そして、多くの親にとって気になるのが、スマホやタブレットの「視聴時間」。これも子どもの脳の発育に影響はあるのでしょうか?
「スクリーンタイムが長いことで、子どもは感情の調整力や共感性が低下してしまい、社会性の発達が阻害される可能性があることも明らかになっています」