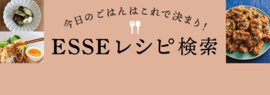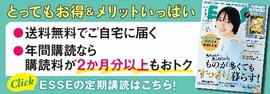ありがたくてありがたくて、本当に心強かった。見ず知らずの土地で、この事態を共有してくれる人たちがいるというだけで、不安がずいぶん和らぎました。
私たちには子どもがいなかったので、家族は2人だけ。その1人の夫が突然いなくなる悲しさと不安を、たったひとりで向き合うのは本当にきつい。だれかが近くにいてくれる。それは、ものすごい安心感でした。
「子どもがいない以上、そんなことはわかっていたはずでは?」と思うかもしれませんが、そんな日は、ずっと、ずっと先だと思っていました。
だんだんと老いて病気がちになって、お互いに闘病や介護があって、80代くらいで亡くなるものだと思っていたけど、それは当たり前じゃなかった。
50歳をすぎたら、いつ、ひとりになってもおかしくないのだと実感しました。
●家はいつものどおりのままだった
夫がいる街に着いたのは、日も暮れかかった夕方。
警察に着くと部屋に案内され、亡くなったあとの状況について説明がありました。スマホ、財布、家の鍵など、貴重品もすべて預かっていてくれて、ひとつひとつ、本人のものかその場で確認しながらサイン。
死因は「致死性不整脈の疑い」。
不整脈が起きてから、心臓が止まるまでわずか数分。すぐそばにAED(自動体外式除細動器)がない限り、救命は非常に難しい心臓突然死のひとつと言われています。私が家にいても、異変に気づかなかったかもしれません。ただ、コロナ禍で会えない間に起こった出来事というのが悔しかった。
警察署の敷地にある、小さな安置室でようやく夫と対面しました。眠っているとしか思えない、とても穏やかな顏。なんだか満足そうな顔にも見える!?
ああ、苦しんでいなかった。よかった…。
でもこれが現実。あの元気で、快活な夫は本当に亡くなってしまった…。
警察まで来てくれた会社の人たちに挨拶をして、ひとまず家に戻ることにしたのですが、部屋の中がどうなっているのか心配でした。でも、玄関を入ったらまったくいつもどおり。寝室を見ても荒れた様子はなにもありません。昼食のあとの食器は、きれいに重ねて流しに置いてあり、冷蔵庫の中には、その日の夜に食べるつもりだったと思われる食材がたくさん入っていました。
ステイホームに備えて、DVDもたくさん借りてありました。亡くなる直前まで、いつもどおりに過ごしてたんだろうな…と思う、普段の暮らしまま。
ひとりで亡くなってしまったけど、決して孤独死じゃない。だれもが理想とする「ピンピンコロリ」を、夫は実践してみせたわけです。
闘病もせず、苦しい顏も見せず、風のように去っていくのもなんだか夫らしいと思うけれど…ただ、ちょっと早すぎる。
ピンピンコロリは20年後にしてほしかったな。
感謝のひと言くらい、言う時間がほしかったな。
いつもと同じ日常、たわいない会話、平々凡々な暮らしの営み。突然の夫の死は、そんな当たり前の毎日がどれだけ幸せだったかを教えてくれました。
【佐藤由香さん】
生活情報ライター。1968年埼玉県生まれ。編集プロダクションを経て、2011年に女性だけの編集ユニット「シェルト・ゴ」を立ち上げる。料理、片づけ、節約、家事など暮らしまわりに関する情報を中心に、雑誌や書籍で執筆。