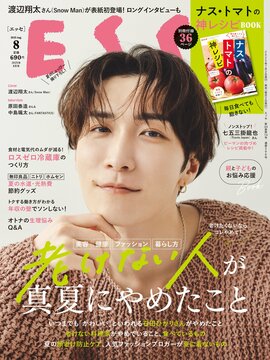残りの人生で、どれだけのお金が必要なのか。自分の寿命はだれにもわからない以上、一度そんな不安を抱き始めると、夜も眠れなくなってしまうものです。でも、きちんと自分の人生をシミュレーションして、必要な費用を計算すれば、その不安を軽減することができるはず。そこで、50代以降の毎日を豊かにするお金の使い方「ゼロ活」を提唱するファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんに、人生におけるお金の不安をとりのぞくための秘訣を伺いました。
すべての画像を見る(全3枚)人生の「年表」をつくろう
「ゼロ活」を実践するうえで欠かせないのが、「自分の老後のシミュレーション」です。はたして、自分が自由に使えるお金はどれだけあるのか、具体的なシミュレーションをしていきましょう。
ポイントは、「今後、自分の人生でいつ、どれくらいの収入が得られ、どのくらいの支出がいつ発生するのか」を把握することです。
では、どうしたら人生の支出を把握できるのでしょうか?
計算を行う上で、役立つのが人生の「年表」を考えてみることです。「自分の未来を年表にしてみる」ことをおすすめします。とくに50代くらいで行うことが効果的です。
でも、「年表をつくる」といわれても、「未来のことだし、どうやって考えればいいの?」と悩んでしまい、いまいちピンとこない方も多いでしょう。
目安として提案するのが、「健康寿命」と「亡くなる方が最も多い年齢(死亡年齢最頻値)」という2つの数値です。
日本人の場合、厚生労働省の統計では、男性の健康寿命はおよそ72歳。男性がもっとも多く亡くなる年齢は約88歳です。一方、女性の健康寿命はおよそ75歳、亡くなる方が最も多い年齢は約93歳です。
これを自分や家族の年齢に当てはめることで、自分の人生がぐっと具体的にイメージできるようになります。
実際に残りの人生を数値化してみたら…
たとえば、私が残りの人生を数値化した場合、どんなシミュレーションを立てることができるのでしょうか。
夫は70歳。データをそのまま当てはめて考えると、健康寿命を迎えるのはあと2~3年後の72歳前後。そのあとは、徐々に医療や介護が必要になる期間に入って、88歳ごろに人生を終えることになります。
一方、66歳の妻は、健康寿命まであと約9年、そのあとは介護や医療を必要とする可能性が高くなり、93歳ごろに亡くなると想定できます。
こうして考えてみると、夫婦で健康に暮らせる時間はこれから18年ほど。そのあとは妻がひとりで暮らす期間が9年ほどになります。
この前提のもとに、残りの人生を「夫婦2人で過ごす前期」と「夫が先に亡くなった後期」の2つにわけ、それぞれの収入や支出をシミュレーションしてみます。「後期」の収入は、遺族厚生年金、老齢基礎年金や私が長年掛けていた国民年金基金、小規模企業共済の積立金などをおもな柱として計画を立てています。
なお、50代で現役の方は、現在の収入や支出の把握は、現在の延長にあるので、老後に焦点を絞ります。