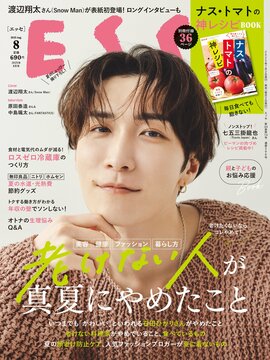暑い日が続いていますが、日ごろの熱中症対策として、どんなことを実践していますか? 暑さに負けない身体づくりのために、きちんと栄養をとって体調を整えておくことが重要です。そこで今回、栄養学的なアプローチからの指導も行う医師の梶尚志先生に、熱中症になるリスクが高い食生活や熱中症対策におすすめの栄養素について、詳しく教えてもらいました。
すべての画像を見る(全4枚)熱中症リスクが高まる「NG食習慣」
熱中症の対策には、水分や塩分の補給や規則正しい生活などが必要だといわれています。とくに避けたい食事にまつわる習慣を紹介します。
●NG1:朝食を抜く
人は寝ている間にも汗をかき、朝起きた時点で、すでに軽い脱水状態になっています。朝食を抜くことで、エネルギー源となる糖質が不足し、体温調節機能が働きにくくなるだけでなく、脳へのエネルギー供給も不十分となり、集中力や判断力が低下する恐れも。
対策は、忙しい朝でも、たとえばバナナやヨーグルト、おにぎり、チーズをのせた全粒粉パンなど、準備がラクで、エネルギー源となる食品を組み合わせるようにすること。
とくに、具だくさんのみそ汁は、塩分・水分・野菜のミネラルを一度に補給できるのでおすすめです。
●NG2:ジュースや甘い飲料を多く飲む
暑い季節は、つい冷たいジュースや甘い炭酸飲料に手が伸びがちですが、これも熱中症リスクを高める原因になります。糖分が多い飲み物は血糖値を急激に上昇させ、体のなかで“隠れ脱水”を起こしやすくなるほか、余計に喉の渇きを感じることもあります。
また、糖分摂取のため、一時的な満腹感から食事の量が減ることで、栄養不足に陥ることも。
水分補給の基本は水や麦茶、もしくは塩分を含む経口補水液です。とくに子どもは「甘い飲み物=水分補給」と思い込みがちなので、普段から麦茶や水を中心に飲む習慣をつけることが大切です。
●NG3:極端な減塩
「減塩=健康」という意識が広まり、塩分を控える人は多いですが、夏場にかぎっては注意が必要です。汗をかくことで、体内の塩分が大量に失われると、体内の水分バランスが崩れ、熱中症のリスクが一気に高まります。
塩分がたりないと、倦怠感やめまい、頭痛などを感じやすくなり、重症化すると意識障害にいたることもあります。
対策は、塩分を無理に控えず、汗をかきやすい日には自然な塩分を意識して摂ることが大切です。
みそ汁、梅干し、塩昆布、漬け物などの日本の食材は、ミネラルも含んだ塩分源としておすすめ。とくにみそ汁は水分補給も兼ねており、毎日の食卓に取り入れやすい一品です。
●NG4:食が細い・偏食
夏はどうしても食欲が落ち、冷たいそうめんなどの「さっぱりしたもの」ばかり食べがち。しかし、これが続くとエネルギー不足やタンパク質不足に陥(おちい)り、熱中症になりやすい“弱い体”をつくってしまいます。
とくに子どもや高齢者はもともと栄養が不足しやすいため、意識的な対策が必要です。
対策は、卵、豆腐、納豆、鶏胸肉、魚など、消化がよく、タンパク質が豊富な食品を意識して取り入れることです。タンパク質は筋肉の材料となり、体温調節機能をサポートするほか、疲労回復にも役立ちます。
冷たいそうめんやうどんを食べる際は、卵焼きや鶏胸肉のほぐし身、ツナ、温泉卵などをトッピングすることで、手軽にタンパク質を補えます。
●NG5:冷たい飲み物・冷菓の摂りすぎ
アイスやかき氷、冷たい飲み物は、摂りすぎると体を冷やしてしまい、かえって体調を崩す原因になります。胃腸が冷えると消化機能が低下し、食欲不振や栄養不足を招きやすくなります。
体力が落ちることで熱中症のリスクが高まるほか、だるさや夏バテの原因にもなることも。
冷たい物を楽しむ際は、“ほどほどの量”を守ることが大切。1日1回までにとどめ、そのほかの水分補給は常温の水や麦茶を中心にしましょう。
食事中や就寝前は、なるべく温かいスープや白湯を取り入れて、内臓を冷やしすぎないよう意識を。
子どものおやつには、寒天ゼリーや果物を使った手づくりアイスなど、自然な甘さかつ冷えすぎないものを選ぶとよいでしょう。