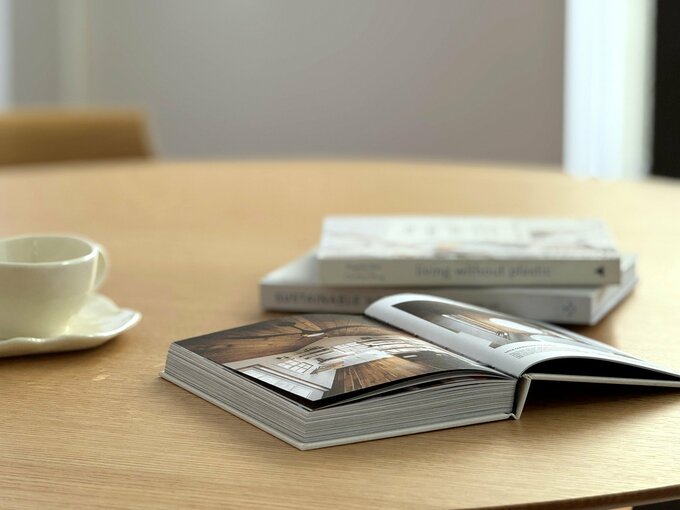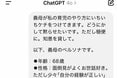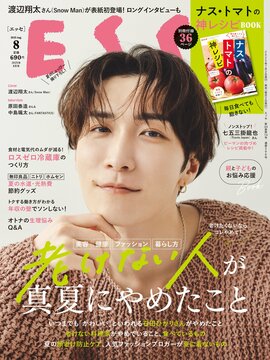生活の変化に合わせて家事の方法や持ちものを見直したことで、自分の時間が増えるなど暮らしが好転した事例を紹介します。整理収納コンサルタント・須藤昌子さん(50代)のケースです。ここでは、須藤さんが実際に見直してラクになったと感じること3つについて語ります。
すべての画像を見る(全4枚)1:掃除は完璧を目指さず、「ほどほどにキレイ」でOK
時間はすべての人の平等に与えられているのに、自分の時間は家事や仕事、介護など、いろいろなことに追われて、あっという間に過ぎてしまうと感じた事はありませんか? 私も、気づけば夕方になってしまい、「今日も自分の時間をつくれなかった…」と悩むことが多くなっていました。
そんなとき、悩みを解決するために考えたのが、家族が寝ている間に家事の大半を終わらせてしまう方法です。
そのひとつが床掃除。家族が寝ている間にすませてしまいたいので、個別の居室がある2Fのフローリングは、音の出る掃除機ではなく、静かに掃除のできるモップを使うようにしています。
本当は、掃除機の方がよりキレイになるのかもしれませんが、スルスルっと床を滑らせるだけで終わるモップでの掃除は、とてもラクなんです。私が目指すのは「完璧なキレイ」ではなく「ほどほどにキレイになり、自分の時間をつくること」。なので、「これでよし」と決めています。
「家事をきちんとこなすのが、ちゃんとした主婦」といったイメージにしばられて、できない自分に落胆するよりも、私は自分ができることを「これでよし」と認めることが、大事だと思っています。
2:個別の食器を使うのをやめて、準備をスムーズに
実家の習慣が元で、結婚後も個別のお箸、ご飯茶碗、汁椀を用意していました。それを、家族で同じ食器を使うように変えました。
子どもが小さい頃は、割れにくい食器や持ちやすい小さなサイズの食器を用意して使う必要もありましたが、子どもが大きくなったあるとき、「食器を使い分ける意味ってあるのかな?」という疑問がわきました。わざわざ、それぞれ専用の食器やお箸を探して取り出すことが、非常に面倒に感じるようになったのです。
このできごとは、無駄な行動をやめて効率よく動き、自分の体力を温存したいという気持ちの表れかなとも感じます。省いても問題ないものやことは、たくさんあると思いますので、自分がラクになるためにも、そういった不要な習慣や思い込みは手放していけたらいいと思っています。