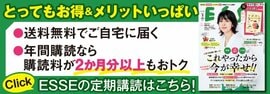気がつくといつの間にか増えてしまう「食器」。食器棚から溢れ、家のあちこちに散らばり収拾のつかない状態になってしまうことも。学生時代に器のおもしろさに目覚め、陶芸作品を扱うショップに勤めた深尾双葉さんもその1人。そこで、「本当に好きなものだけ」と決めて捨て活を行い、現在は6つのルールで食器を持ちすぎないよう管理しているそう。築35年の賃貸で夫婦ふたりで暮らす深尾さんに食器の持ち方についてお聞きしました。
すべての画像を見る(全7枚)1:器の色は白、黒、染付の青をメインに
色とりどりの食器を手放し、白、黒、染付の青の3種類をメインカラーとして、色数を限定しました。
鮮やかな色は料理から取り入れると割り切ることで、器を華やかにしなければいけない、料理ごとに器を替えなければいけないというしがらみからようやく解放されたように思います。
白ひとつとっても青みがかっていたり、かすかに赤を感じるもの、そして古物ならではの味のついた景色が楽しめたりと、同じ色でもそれぞれに表情は異なります。色の数を増やすのではなく1色の奥行きを楽しむことで、食器も増え過ぎず管理もしやすくなると思います。
2:木製の器は漆器を選ぶ
木製の器が好きで、今までも数多く試してきました。木肌そのものを生かした器は存在そのものがかわいらしく、眺めているだけでも心豊かになります。
しかしズボラな私はこまめな手入れを怠り、その結果シミをつくったり、ささくれ立つほどまでに乾燥させてしまったりと、今振り返ってみてもよいつき合い方ができていたとは言えません。
そんな自分の性格に合っている器が「漆器」です。特にふき漆仕上げのものは並べたその日から食卓になじみ、指紋や傷もさほど気にすることなく使えます。たとえ落として欠けてしまっても、新品同様に修復可能。水や油染みもつかない。軽く口当たりも優しく、熱々の汁物をよそっても火傷をしない。木製食器の良さも十分に感じられる。日本が誇る優秀な手仕事だと感じています。
3:何とおりにも兼用できる器を選ぶ
食器棚で目指していることは100%の稼働率です。数年に1回しか活躍しない器、使い方の限定された器はほぼ手放したため、今はその目標に近づきつつあります。
大切なのは何とおりもの使い方がイメージできる器であるということ。
たとえば、そば猪口は、お茶、お酒、料理、デザートと多くの場面で使えるため優先して手元に残したい器です。逆に洋の要素が強すぎる器は、使い方が限定されてしまうため手放しました。家の中の食器は和洋中、料理のジャンルも限定せずに組み合わせて使うことができるもので揃えています。
1週間のうちに全ての器が、お茶や食事の時間に登場すると、埃が積もったりガラスが曇ることもなく、常に美しい状態の食器棚を保つことができます。しまい込まれていたときより格段によい表情に見えるから、ものというのはなんとも不思議です。