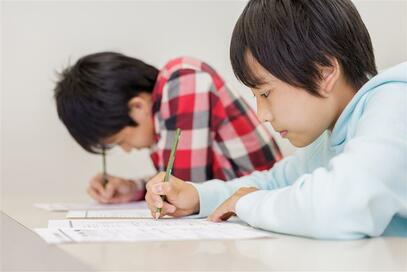野菜やお米などの値上がりが続いていますね。家計がさらに厳しくなったと実感している方も多いのではないでしょうか。そこで、今日から実践できる「食費節約のコツとリアルな献立」を伝授します。紹介してくれたのは、50代の夫婦ふたり暮らしで栄養士として働いた経験をもつ本多めぐさんです。
すべての画像を見る(全8枚)節約のキモは「安い食材を知る」こと。まとめ売りは単価を計算
ここでは物価高の今、食費を抑えながら満足できる献立を立てるコツをお伝えします。いつも食材の買い物をしていて、野菜やお肉といった定番食材の値段を覚えている方も多いのではないでしょうか。たとえば大根1本が198円、豚ひき肉が100gで120円というふうに、その価格をもとに買い物をされていると思います。しかし、普段買わないものは値段を覚えていないので、多少高値でもカゴに入れてしまうことがありませんか? 私の場合は、レンコンやカボチャなどが当てはまります。
そして、値段を覚えていないとお店のポップに惑わされます。店頭で「サービス品」「特売品」と書かれていても、実際はあまり安くないことがあります。また、「3つで○○円」のようなまとめ売りで値段がわからなくなることも…。
そこで私が心がけているのは、とにかく焦って買わないこと。安いかどうかわからないものは無理して買わないと決めています。単価はスマホの電卓アプリで計算できますし、その日は諦めて帰って、別メニューにしてもよいのです。
●季節商品の値上がりには要注意
また、季節にちなんだ商品が高額になっていることも。お正月商品がわかりやすい例です。かまぼこや黒豆などの安い商品が、12月になると豪華で高額な商品になって、数百円値上がりするのです。
しかし、元値を知っていれば、本当に今買うべきか判断ができるはず。黒豆やかまぼこの代用品はないか。かまぼこでなくても、ほかの練り物を工夫して豪華に見せてはどうか。可能なら31日の夕方以降や元旦まで買い物を待ち、割引を狙ってみてはどうか。どうしても正月料理を全部並べて食べなくても、一品くらいなくても構わないのではないか…という選択肢が生まれます。
つまり「食材ごとの単価をだいたい覚えておく」と、代替品を取り入れたり買わないと決めたりして、安い商品だけを買うことができます。
ジャガイモを長イモで代替。安い食材を都度組み合わせ
節約ルールの2つ目は「柔軟に安い食材を組み合わせること」です。たとえば欲しい野菜が高い場合は、似た野菜で代用します。カレーライスに使う牛肉を鶏肉や豚肉にするように、野菜なども柔軟に変えることで食費が抑えられます。
私がよくやるのは、イモ類の変更です。たとえば肉ジャガやカレーライスは、ジャガイモにこだわらず、そのときに安いイモ類をチョイス。サツマイモや長イモなどでつくります。葉物野菜は、元のレシピがホウレンソウなら、小松菜、チンゲンサイなどで代用します。冷凍ホウレンソウが安ければそちらを選ぶことも。
さらに献立も積極的に変更してみましょう。たとえばピーマンの肉詰めの予定で買い物に行ったら、ピーマンが高値だった。そのときはナスやレンコン、タマネギのはさみ焼きにしています。献立の変更はハードルが高く感じるかもしれませんが、ネットでレシピを検索すればレパートリーが少なくてもなんとかなります。
「常に店頭で安い商品を選ぶ」「その組み合わせで食事をつくる」以上の2つのルールを守ることが食費節約につながります。