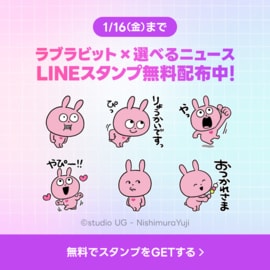受験結果が希望と違っても「前向きな気持ち」で入学できる声がけが重要
すべての画像を見る(全3枚)そして、後藤さんが始め方以上に重要というのが、受験の終え方。子どもが「この中学に入れてよかった!」というポジティブな思いを抱いて入学させるのが、中学受験における親の最重要ミッションだと話します。
「中学受験はゴールではなく、中高生活のスタート。その先の人生の方がずっと長く、重要です。ですから、もし第一志望に合格できなかったとしても、まずは一緒に伴走してきた大人が、『じつはあなたにいちばん合っていると思っていたから、この学校に入ってくれてうれしい』と伝えてあげてください。仮にそれが本心ではないとしても、そのひと言で子どもの心もちは変わってきます」
また、受ける学校のうちどこに進んでも成功と思えるよう、受験校を決定する際には、絶対に“滑り止め”という言葉を使わないことも大切といいます。
「第二、第三と序列をつけるのもできるだけ控えたほうがよいでしょう。自分たちにとっては志望順位が低い学校も、誰かにとっては第一志望かもしれません。学校の優劣を植えつけないことが、結果的に子どもが肯定感をもって中学に進学することに繋がります」
受験塾を特別視せず、「思考力」を得られる習い事と考える
後藤さんによると、第一志望に進学できる子どもの割合は、数年前までは3人に1人、昨年は4人に1人程度だったとのこと。
今後は、少子化の影響や、学校の多様化で志望が分散していくことにより、ややその割合が増加していくことが予想されるそうですが、やはりいわゆる人気校に入学するのはかなりの狭き門。結果次第では、かけたお金や時間がムダになってしまうと考える親もいるかもしれません。
しかし、単なる暗記ではなく、知識を使ってその場で考える入試問題が増えた現在、受験勉強で身につく思考力は、その後の大学受験などに間違いなく役立って行くと、後藤さんは力説します。
「たとえば、中学入試のどの教科でも、問題文に表などの資料が含まれ、その中から必要な情報を抜き出し、それを使って答えを導き出すという問いが増えています。また、相反する双方の立場に立って意見を述べよという、共感力や想像力が必要な出題もあり、こういった問題を解くことによって、子どもの“考える力”が相当鍛えられます。それだけでも、受験勉強には価値があるのではないでしょうか。『思考力』を伸ばす習い事と考えれば、塾に通う2、3年はとても価値のあるものになるはずです」
そして、最終的に公立中学校に通うことになったとしても、積み上げた知識や考える力は、高校受験に向けての大きなアドバンテージとなるともいいます。
「第一志望に進めたら確かに最高ですが、そうではない結果となった場合も、受験勉強で得られることは多いということを知っておいてください」