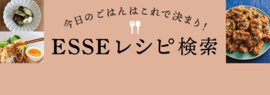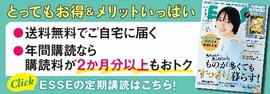「子育てには大変も幸せも両方あって、おおむね幸せ。話すほどではない幸せは、ちゃんとある」と話すのは、ESSEonlineでヘア連載を執筆中のライター・佐藤友美(さとゆみ)さん。さとゆみさんは息子と2人暮らしです。
そんなさとゆみさんが子育てエッセイ『ママはキミと一緒にオトナになる』(小学館刊)を上梓。今回は自身の父親(息子にとってのおじいちゃん)が息子と接する中で思い出した「父の言葉」について、同書を抜粋し、紹介します。
「待てる親」になりなさい
すべての画像を見る(全3枚)昨年亡くなった父は、小学校の教員だった。
あれはいつのことだったか。上京した父と一緒に公園の近くを歩いていたときのこと。少年野球をしているグラウンドのほうから、コーチらしき男性の大きな声が聞こえてきた。
「どうしてそんな大事なところで、ミスするんだよ!」
その声を聞いて、父は顔を曇らせた。
「子どもだって、ミスしたくてしてるわけじゃないよなあ。『どうしたらミスしなくなるのか、教えて、先生!』って言いたい気持ちだと思うよ」
父は、子どもたちが「できない理由」を、とことん考える人だった。
たとえば、「昨日の遠足、どうだった?」と聞くと、クラスの子たちは我先にと感想を伝えようとするのに、それを作文に書いてというと、突然固まってしまう。話し言葉と書き言葉にはどんな違いがあるのだろう。何が子どもたちを書けなくさせているのだろう。
そう考えた父は、独自の作文指導法を考えた。たとえば語彙を増やすゲームをするとか、正解不正解のある助詞を使わないとか、型を教えてそれに当てはめてみるとか。子ども目線で考えられた作文メソッドは、物書きの私から見ても、とても斬新で本質的で勉強させられた。
●自分の子どもが左利きかもしれないなんて考えたこともなかった
息子氏が左利きであることを、最初に見抜いたのも、父だった。
あれは彼が三歳になる頃のことか。実家に連れて帰ったときに、母と私で彼をテニスコートに連れて行ったことがある。私たち家族は全員ソフトテニスをするので、息子にもラケットを持たせてみようと思ったのだ。
ところが彼は、驚くほどの運動音痴だった。ボールが目の前をゆきすぎてからしばらくたって、ラケットを振る。いち、にっ、さん、と声をかけるが、タイミングが全然あわず、ラケットにあたる気配がない。
家に帰ってからそのことを父に伝えると、「ふーん」と聞いていたが、次の日、父は彼をテニスコートに連れ出した。
私はそのとき、同行しなかったのだけれど、帰ってきた父は、
「ゆみ、この子、左利きだぞ」
と言ったのである。
父はどうしてラケットにボールが当たらないのかを観察していて、はたと、右手では打ちにくいのかもしれないと思ったそうだ。ラケットを左手に持ちかえたら、突然ボールが打てるようになったという。
それまで、自分の子どもが左利きかもしれないなんて考えたこともなかった。運動神経が鈍い子なんだなと思った私と違い、父は、できない理由はなんだろうと考えた。さっさと子どもの限界を決めて見限った自分が恥ずかしくなった。この頃から彼は、スプーンもクレヨンも左手で持つようになった。テニスラケットを振った感覚から、こっちのほうが楽だ、と気づいたのだろう。