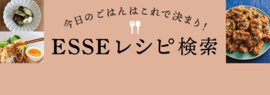今は夫や子どもたちに囲まれる賑やかな生活でも、私たちはいつか一人になる可能性があります。そのタイミングは思ったより早く、望まない形で到来するかもしれないし、老後に訪れるかもしれません。必要なのは、いつ「一人」になっても前に進めるように生きていくこと。
36歳で夫と死別し、2人の子を育て上げ終わった後のシニアのひとりでの生き方をつづったエッセイ集『
』(扶桑社刊)の著者でシニアブロガー・りっつんさん(62歳)にお話を伺いました。
すべての画像を見る(全5枚)30代で未亡人に。一人暮らし12年を振り返って思うこと
36歳のときに当時38歳だった夫と死別。50歳のときに2人の息子が独立し、人生初となるひとり暮らしを始めたりっつんさん。現在はその暮らしぶりを発信し、シニアブロガーとして活躍しています。そんなりっつんさんに、現在に至るまでのことを教えてもらいました。
●がん発覚から旅立ちまで5年間、心の準備は全然できていなかった
夫を亡くした当時、子どもはまだ10歳と8歳。りっつんさんはどのように乗り越えたのでしょうか?
「夫の胃がんが発覚したのは、亡くなる5年前。夫は『殺しても死なないくらい丈夫』と言われるほど元気で症状は一切なかったので、青天の霹靂でした。二人の子も、上の子は幼稚園、下の子はまだ家にいる年齢なのに、がんのステージはⅢの終わり、つまり末期に近い進行がんでした。その後、手術して一時は落ち着いたものの、数年後に再発。それから10か月後、心の準備ができないまま夫の死を迎えました」
初七日の法要が終わると、一気に寂しさと疲れが襲来。このとき、思いがけない人がりっつんさんを救ってくれました。
「晩ご飯をつくる気にもなれず、茫然自失としていた時、家のチャイムが鳴りました。ドアをあけると、そこには当時小学生になっていた長男の同級生のママが、バスケットを抱えて立っていたのです。『よかったらどうぞ』と言って渡してくれたバスケットには、なんと、中華ちまきがぎっしり。晩ご飯をつくる気になれないだろうと、手間のかかるちまきをわざわざつくって持ってきてくださったんです。その方とは、偶然会えば少し話をするくらいの知人だったのですが、子どもを通じて今回の不幸を聞いて、心配してくださったようです。この心遣いが、身に沁みて嬉しかったし、『なにかあったらこの人を頼ってもいいかな』と思え、心強く思いました」
夫を失ったばかりのとき、頼れそうな人が現れて、救われるような思いだったと話します。
「今にして思うと、そういえばいつもだれかがいてくれて、いろんな人たちから少しずつ助けてもらいながら生きてきた気がしますね。だから私は、自分だけで夫の死を“乗り越えた”のではなく、周りの人たちが見守るなか、“流されるままにただ生きてきた”という感覚でいます」
●流れに身をまかせながらも持ちづけていたもの
とはいえ、流されながらも、ある強い意思はもっていたと言います。
「『子どもたちが成年を迎えるまでは死なない』という意思です。当時二人の子は10歳と8歳。私が死んだら二人はみなしごになってしまう。なにがあってもそうなってはいけないと思い、夜中に本気でお祈りしたことがあります。『次男が20歳になるまでは生き延びさせてください。その代わり、それ以降なにが起きても文句を言いません』と。また、私が生き延びただけでなく、彼らが自分の力で食べていける人になってほしいし、そうなってもらわないと困る。この使命感が、生きる原動力になったと思います」
●3度目の家族の巣立ちを前に、準備してきたこと
そうしてりっつんさんは、自宅でできる仕事に限定して、仕事を複数かけもちしながら子育てにまい進。長男、次男ともに大学進学し、就職して巣立って行ったのは12年前でした。
母親のなかには、子が巣立ったあと、虚脱感でつらくなったり、抑うつ症状が出る「空の巣症候群」に悩まされる人もいます。りっつんさんの場合、夫に続く二度目、三度目の「家族の巣立ち」に対し、どう対処してきたのでしょうか?