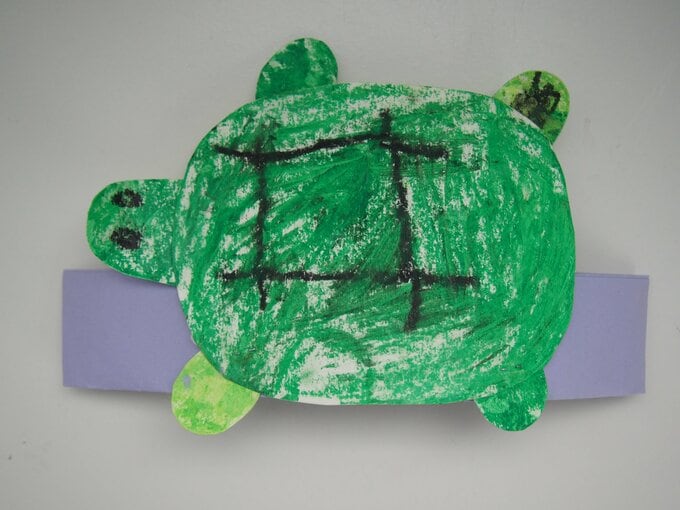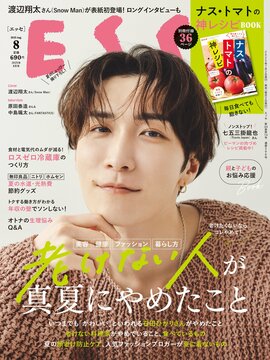子どもがオモチャを出しっぱなしにして「片付けなさい」と何度言ってもなかなか続かない…そんな悩みをもつご家庭は多いかもしれません。ここでは、整理収納アドバイザーのFujinaoさんが実践している、子どもも片付けやすい仕組みをつくるコツについて語ります。夏休みに行うのもおすすめです。
すべての画像を見る(全5枚)成長段階の子どもには「できなくて当たり前」の目線を
子どもはまだ片付けを学んでいる途中です。今日は手放せなかったオモチャも、1か月後にはすんなり手放せることもあります。無理に手放しを迫ると逆効果になりがち。まずはあせらず、親が見守る姿勢が大切です。
なかなか減らせないタイプの子には、一度に大量に減らすのではなく少しずつ何度も見直す機会を設けるのがおすすめです。
まずは「全出し」。量を減らせば、片付けは簡単になる
オモチャ収納を見直す第一歩は、すべてを一度出して「見える化」すること。家じゅうに散らばっている場合は、一度1か所に集めましょう。その後、「最近遊んでいない」「壊れている」「興味が薄れた」ものを手放します。
ものの量は、多すぎると片付けのハードルが上がり、苦手意識につながります。子ども時代に苦手になると、大人になってもそれが残ることもあるため、「量を適正に保つこと」にはとても価値があります。
子どもと一緒に整理する場合は、「これ、まだ遊びたい?」「お友達にあげてもいいと思う?」「これ、宝物?」「もう卒業してもいい?」などの声かけをするのもおすすめです。
出し入れしやすい収納システムをつくる
収納のコツは、出し入れのハードルをできるだけ下げること。たとえば、放り込むだけでOKな収納にする、細かく分類するよりも「ぬいぐるみ」「ブロック」「おままごと」など、ざっくりしたカテゴリ分けにすると片付ける時のハードルが下がります。
また、箱や引き出しにはラベルをはっておくと視認性がアップします。まだ文字が読めない子には写真ラベルが効果的。オモチャの写真をはることで、視覚的に「ここに戻す」ことが理解しやすくなります。