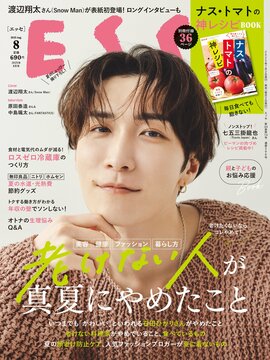習いごとに遊び時間、さらには中学受験…。忙しい子どもたちの家での学習環境をどう整えるかについて、日々悩んでいる家庭も多いのではないでしょうか。今回は、小学生を対象とする非認知能力専門塾「Five Keys」を設立したリザルトデザイン株式会社 代表取締役の井上顕滋さんに、心理学や脳科学の観点から、小学生の家庭における学習環境を最適化する方法を教えていただきました。
すべての画像を見る(全4枚)子どもの発達に影響を与える「幼少期の環境」4つ
家庭の学習環境や生活習慣は、子どもの脳の発達や非認知能力に大きく影響します。非認知能力とは、テストなどで数値化できない能力を指します。たとえば、意欲や自制心、共感力、集中力などです。ここでは、幼少期の家庭環境や生活習慣が、子どもの発達に影響を与える例を4つご紹介します。
●1:「親の温かい関わり」でストレスに強い子どもに
とくに、親による、温かく支援的な関わりは重要です。ワシントン大学ジョアン・ルビー博士らの研究(※1)では、幼少期に心理的に十分な養育を受けた子どもは、学習や記憶、ストレス調整に重要な脳の領域(海馬)が有意に発達することが示されました。
●2:「読書や旅行などの体験」によって脳が発達
また、ペンシルベニア大学のブライアン・B・アヴァンツ氏らの長期調査(※2)では、4歳ごろに本や会話、旅行や音楽といった環境刺激を多く受けた子どもは、10代後半で言語や認知機能を司る脳の領域がより発達することがわかりました。
●3:「騒がしく散らかった環境」で育つと自己制御力が低下
物理的な環境も無視できません。複数の大学によるアメリカの研究チームが行った1235家族を対象とした研究(※3)では、騒がしく散らかった家庭で育つと、5歳時点での認知能力や自己制御力、社会性という非認知能力が低下する傾向が示されました。
混乱した環境は親子の質の高い関わりを妨げ、子どもの集中力や非認知能力を低下させる要因になるのです。
●4:「不規則な生活習慣」により学習効率が低くなる
生活習慣の規則性も重要です。ロンドン大学のイヴォンヌ・ケリー教授らによる1万1178人の幼児を対象とした縦断研究(※4)では、幼児期に就寝時刻が不規則だった子どもは、7歳時点で読解力・数学力・空間認知能力のテスト結果が低く、不規則な生活が脳の発達や学習効率に悪影響をおよぼすことが示されています。