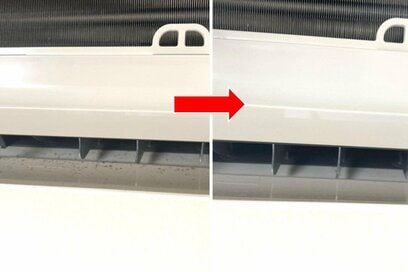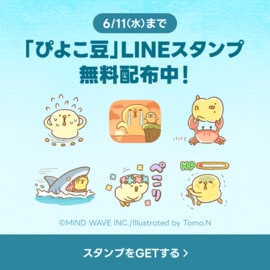日々の生活で、「こんなはずではなかった」なんて思ったことはありませんか? そんな迷いや物たりなさを感じたときにこそ、「禅」の教えが役立つかもしれません。今回は、YouTubeチャンネル「大愚和尚の一問一答」で人気の僧侶・大愚和尚の書籍から「平常心」という禅語を抜粋してご紹介します。何気ない日常を見つめ直し、心を豊かにするヒントが満載です。
一瞬一瞬の真剣勝負が圧倒的な差を生み、異彩を放つ人になる
「平常心」とはなにか。禅の世界においての”平常”とは、現代人が寝転がってテレビを見ているというような日常とは異なります。いつも真剣勝負、命をかけて修行する禅僧の日々が、この言葉の意味する”平常”です。
趙州和尚がまだ修行をしていたときのことです。師匠である南泉(なんせん)禅師に、「道とはなんでしょうか?」と問います。禅師は、「平常心是道(平常心、これ道)」とおっしゃいました。
茶道、華道、書道、武道に「道」とあるように、一所懸命に、つまり一所に命をかけて、極めていく学びに、この「道」という字がついています。そして、命がけで修行を積む日常のあり方がそのまま「道」である、と南泉禅師は修行中の趙州和尚に伝えたわけです。
このように平常心が「道」というと、特別に名を成す人のための禅語で、自分には難しいと感じる方も多いかもしれません。けれど、平常や日常はだれにでも平等に与えられています。
1日24時間は、変わりません。日常をどう過ごすかで未来が変わっていくのだ、ということを私はこの言葉でお伝えしたいのです。
日常の小さなことにも心配りができるということは…
明治の文豪、幸田露伴の娘・幸田文さんのエッセイの中に、こんなエピソードがあります。幸田文の『しつけ帖』(平凡社)の「水」という章です。
露伴は水を侮(あなど)ってはいけないと言って、娘にぞうきんがけのなんたるかをしつけました。どういうことかというと、ぞうきんがけをするときに、バケツの上でぞうきんをギュッと絞ると、どうしても水滴が周囲に落ちることがあります。
とくに小さな子どもの場合は「仕方ない」ですむことです。しかし露伴はひとつの滴が落ちることも許さなかったのです。つまり、ごく日常の動作である雑巾を絞るときも真剣勝負というわけです。
私はこのぞうきんのエピソードに少し驚きつつも、ぞうきんを絞る一瞬に細心の注意を払う、これこそが「平常心是道」の実践だと深く共感しました。なぜなら、それをしつけられた人は、最後にワタワタと床に落ちた水滴を拭(ぬぐ)うことはありません。バケツを引っくり返すような大事に至ることもないでしょう。
日常の小さなことにも心配りができるということは、常に心が静かで、それが日常の些事(さじ)であっても、自分自身の目標へ向かうときであっても、淡々と進め、実行することができるのです。
目の前の小さなことでも真剣勝負で極めることで、学びや気づきが生まれます。どんな些細なことにもドラマがあるとわかるのです。