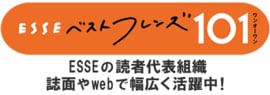都市部を中心に加熱する「中学受験」。子どもの将来を考え、中学受験をした方がいいのか迷う人も少なくないのではないでしょうか。とはいえ、中学受験を検討するにあたり、「早生まれ」や「晩熟タイプ」は中学受験では不利になってしまう、と教育系インフルエンサーの「東京高校受験主義」こと東田高志さんは語ります。中学受験に向いている子とそうでない子の違いについて、東田さんに詳しく教えてもらいました。
すべての画像を見る(全5枚)早生まれや晩熟タイプは不利?中学受験のリアル
まずは、どんな子どもが中学受験に向いているのか見ていきましょう。
中学受験への適性を見極めるためには、子どもの成長の特性を把握することが大切になります。結論を先に言うと、知的好奇心が強く、心の成長が早い「早熟タイプの子ども」は中学受験に向いていると言えます。
川口大司先生(現・東京大学大学院教授)は、『誕生日と学業成績・最終学歴』という論文で、中学生よりも小学生において、女子よりも男子において、相対的な年齢が学業成績に強く影響を与えていることを明らかにしています。
早生まれや晩熟タイプの小学生は、精神的な成長度合いが同級生よりもゆっくりで、努力だけではその差を埋められずに、中学受験では不利になってしまうことがあるのです。
難関私立中学の合格率ほど、生まれ月に大きく左右
これを裏づける関西の私立中学の最難関・灘中学校合格者の生まれ月のデータがあります。
4月~6月生まれの子どもは197人が合格(全体の36.4%)という結果に対し、10月以降に生まれた子どもの合格者は大幅に減少し、1~3月生まれにいたっては、合格者はわずか76人(全体の14.1%)にとどまります。
中学受験の場合、入試による選抜時期が早すぎて、生まれ月が学業成績に直接的な影響を及ぼしているのです。
もっともわかりやすいのは国語の読解問題です。中学受験は「大人度」を測るテストです。「恋愛感情」をテーマにした小説の出題がその象徴と言えます。
難関私立中学の入試では、三島由紀夫の『豊饒(ほうじょう)の海』が出典だったこともありました。こうなると、努力量よりもむしろ、生まれもって定められた“脳の成長の早さ争い”になってしまいます。
逆に高校受験では早生まれが有利に?
しかしこのハンデも、15歳まで待てば成長の差が埋まってきます。小学校では体の小さかった子が中学で急激に成長し、言動も大人びていくのを目の当たりにしたことのある人も多いのではないでしょうか。
高校受験のトップ校・都立国立高校の2023年度新入生161人の誕生月を独自で調べたところ、4~6月生まれが27人、7~9月生まれが53人、10~12月生まれが35人、1~3月生まれが46人と、受験で不利と言われる早生まれの割合が高いという結果になりました。
早熟タイプの秀才が中学受験で抜け、晩熟タイプが相対的に有利になった可能性を示す興味深いデータです。