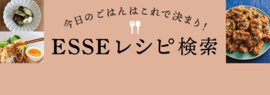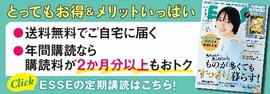読者から届いた素朴なお悩みや何気ない疑問に、人気作『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社刊)の作者・菊池良さんがショートストーリーでお答えします。今回は一体どんな相談が届いているのでしょうか。
すべての画像を見る(全4枚)ここはふしぎなお悩み相談室。この部屋には世界中から悩みや素朴なギモンを書いた手紙が届きます。この部屋に住む“作者”さんは、毎日せっせと手紙に返事を書いています。彼の仕事は手紙に書かれている悩みや素朴なギモンに答えること。あらゆる場所から手紙が届くので、部屋のなかはぱんぱんです。
「早く返事しないと手紙に押しつぶされちゃう!」それが彼の口ぐせです。
相談に答えてくれるなんて、なんていい人なんだって? いえいえ。彼の書く返事はどれも想像力だけで考えたショートストーリーなのです。
さぁ、今日も手紙がやってきましたよ──。
【今回の相談】必要なときに限って探しものが見つからない
必要なときに限って探しものが見つかりません。この前もペンを使おうとしたら、差していたはずのペン立てにないのです。そのときはあきらめて別のペンを見つけだして使ったのですが、後日ペン立てを見るとなかったはずのペンがあるのです。なんでこんなことが起こるのでしょうか?
(P.N ワンダさん)
すべての記憶は曖昧だから
わたしの最初の持ち主は雑貨屋でわたしを買い求めた。それがワンダだった。
ワンダはわたしをつくえのうえのペン立てに差していたが、あまり使うことはなかった。ふだんは電子機器を使っていて、手書きが必要になったときだけわたしを使った。それはめったになかった。
わたしはワンダがせわしなくなにかしているところをペン立てから眺めることが日課になった。
あるとき、ワンダが友人を部屋に連れてきた。ふたりはテレビを見ながらお酒を飲み、尽きることのない会話をしていた。やがてふたりで映画を見に行こうとワンダが言い出した。友人は鞄のなかから手帳を取り出して、予定を確認した。来週末なら都合がいいと返事をすると、ワンダは喜んだ。友人は手帳に予定を書き加えようと、手帳カバーのペン差しに指を這わせた。しかし、ペンがない。
「ねえ、ペン貸してくれない?」
「ああ、そこのペン立てにあるよ」
ワンダはわたしを指さした。
友人は手帳に新しい予定を書きつけると、わたしをペン立てに戻さず手帳カバーのペン差しに入れた。ついいつものリズムでしてしまったのだろう。そして二番目のわたしの持ち主になった。
二番目の持ち主は、わたしを持ち帰ってしまったことに気がつかなかった。ワンダもわたしがいなくなったことに気がつかなかった。いや、気づいたのかもしれない。ペン立てにわたしがいないことに気がついて、「あれ、どこにやったんだろう」と。しかし、すぐに新しいペンを買ってしまったに違いない。
二番目の持ち主はわたしを頻繁に使った。手帳に予定や思いついたことをメモすることが習慣だった。だから、わたしはいろんな場所に連れていかれたし、たくさんの景色を見せてくれた。初めて海外にも行った──灼熱の砂浜で見た海の青さを、わたしは忘れない。
わたしと持ち主は長い時間をいっしょにすごした。
しかし、別れは突然にやってきた。たまに散歩でやってくる公園のベンチ。そこに腰掛けて、思いついたことをメモしていた。いつものようにわたしをペン差しに戻す。そのとき、指の位置がずれてしまった。
わたしは地面へと落ちた。生えていた雑草が音を吸収した。なにも音はしなかったので、持ち主は落としたことに気がつかなかった。そして、わたしに背を向けて歩き去っていく。
わたしは声をあげたかった! 持ち主の背中に向かって、力のかぎり叫びたかった。助けを呼ぶ赤子のように。その声に気がついて振り向く持ち主の顔が見たかった。わたしは立ち上がろうとした! この身体を持ち上げて、持ち主のところへ駆け出したかった。草原を駆ける動物のように。しかし、できなかった。わたしはペンなのだ。わたしは横たわっているしかなかった。