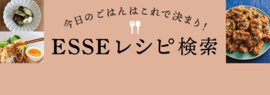なかなか売れないと言われるノンフィクションの分野で、ある本が脚光を浴びています。高橋ユキ著、『つけびの村 噂が5人を殺したのか?』(晶文社刊)。WEBで話題を呼んだことがきっかけで書籍化、しかも書き手は一児の母でもある女性という一冊です。
出版に至るまでの経緯や、事件ノンフィクションを取り巻く状況について、高橋さんにお話を伺いました。
なんとか時間を捻出して、東京から遠く離れた場所での取材を繰り返した
2013年夏、山口県・周南市の集落で5人の村人が殺害された「山口連続殺人放火事件」。山奥の寂れた村へIターンした男性が起こした殺人事件は、当時「現代の八つ墓村」として、ワイドショーやSNSでセンセーショナルに扱われました。
しかし、日々ものすごい速度で更新されるニュースの波に流され、もはや記憶に残っている人も少ないのでは。この事件が再び注目されることになったのが、高橋さんの「note」(※WEB投稿サービス)への投稿でした。
●謝恩会の準備をしている傍らで、購入通知がすごいことに
もともとある雑誌の取材で、現地に赴いた高橋さん。そのときは「山口連続殺人放火事件の舞台となった村には、『夜這い』の風習があるらしいので調べてほしい」という依頼でしたが、村には「夜這い」とは別に、テレビやネットのニュースには載っていない事件の謎が残っていることに気づき、独自に取材を進めます。
取材した内容をまとめ、ノンフィクションの賞に応募したものの、落選。出版社に企画を持ち込んでもよい返事は得られず、宙ぶらりんになっていた原稿を「note」に有料記事として投稿してみることに。
最初はあまり注目されなかったものの、今年3月に突如Twitterを中心にバズが起こり、一躍話題に。その頃、高橋さんは息子さんの保育園の謝恩会の幹事で慌ただしくしていましたが、「パパたちが踊る『U.S.A.』の完成度をチェックしているところに、ひっきりなしに購入通知が届いた」といいます。
――この本の出版経緯は新しい形だと思います。高橋さんがずっと諦めなかったのがすごいと感じました。「じつは、いったん書き上げたあとは、諦めていたんです。でも事件の節目の年に、話を聞かせてくれた方が亡くなられて、形にしたいという想いは強くなりました。でも紙媒体には掲載先がなく、ウェブに投稿することにしたんです。『note』って、生き方エッセー、仕事のハウツーコラムが多いんですが、そんな場所で、ノンフィクションがどう受け止められるのかという単純な興味もありました。
あと、夫が厳しかったんですよ。『お前は子どもを俺に預けて何回も遠方の山奥に行ったのに、仕事にできてない』と(笑)」
●治一郎のバウムクーヘンとラスクを手土産に取材へ
――小さなお子さんを抱えながら、東京から何時間もかかる山口県で取材活動を続けるのは、大変だったと思います。「夫やファミサポなどの託児サービス、懇意にしているママ友など、使えるカードをなんとか組み合わせながら時間をつくっていました。夫も雑誌の仕事をしているので、仕事内容も私の取材に対する熱意も理解していましたが、この事件が“売れるもの”になるかどうかについては懐疑的でした。それゆえ『やっても仕方ないのでは』という態度になったんでしょうね」
――ネットスラングで、「嫁ブロック」という言葉があります。既婚男性が、転職や独立など、新たなチャレンジに取り組もうとするとき、奥さんが家庭の生活の安定のために「待った」をかける状態のことを指しますが、同様に、自分のやりたいことを夫によって制限される「夫ブロック」なるケースも、じつは少なくないように感じます。「夫は文句を言いながらも、子どもの面倒をみてくれたので、そこまでではなかったです。ただ実際、託児サービスに預けると取材費以上にお金がかかりますし、どうしても『ここまでやる必要はないかな』と、自分でストップをかけてしまうこともある。今回は行くと決めたからがんばってみようと、思いきってやりくりしました」
――会えるかどうかわからない取材相手たちへのお土産に、「治一郎」のラスクとバームクーヘンのセットを買い込んで、新幹線に乗り込む描写が印象的でした。「軽いのに箱が大きくて立派なので、『すごいものを持ってきた』って思われやすいんです(笑)。手土産もデパ地下でいろいろと試して、値段とか内容を比較して、最終的にこのセットに落ち着きました。日持ちもしますし、ちょうどいいんです」
書籍化することでノンフィクションを盛り上げたい
――今回書籍化することにしたのは、ノンフィクションを盛り上げたいという気持ちがあったそうですね。「課金してもらったお金で追加取材して、それをまた『note』にあげることも考えましたが、昨今のノンフィクション媒体への危機感もあり、書籍化することで少しでもジャンルが盛り上がることにつながるなら…という気持ちがありました」
●最後に謎が解決しなくても、それがむしろリアル
――書籍版は、追加取材で明らかになった新事実が盛り込まれるなど、大幅に加筆されています。ただしすべてが解決するわけではなく、謎が謎のまま残っているのも本書の特徴です。「一般的に評価されているノンフィクションは、社会問題を反映していたり、読んだあとになにかしらの“気づき”を得られたり、という傾向があると思います。『犯人のような人間が生まれたのは、家族に問題があったからだ』とか。でも、全部が全部そうじゃないと思っていて。この『つけびの村』は、伏線はあまり回収できていません。謎が謎のまま残っているんですが、それには批判的な声もありますが、受け入れてくださった方はそれがリアルだと感じてくださったのかもしれません」
――小さな集落の「うわさ話」。だれしもが経験のあることを発端にして、やがて凄惨で理不尽な殺人事件へ…。そこに至るまでの数々の謎、そしてそれを盛り上げる緻密な筆致が、ドキュメンタリー映画を鑑賞しているような臨場感を与えてくれます。そういった「臨場感」も、たくさんの人の心に届いた理由かもしれません。「取材の現場で感じた、『犯人はいなくなったけど、噂はまだ続いていく』という空気を伝えたかった。出してみて、地方の方からの反響が多いですね。『うちの地元もこんな感じです』とか。あと、女性読者も多かった印象です」
――このような形でヒット作が出ることは、ノンフィクション本だけでなく、出版の世界全体で考えても、喜ばしいニュースだと思います。「ただ、この本が出せたのも、もともとは取材費を出してくれた週刊誌の存在があったからです。今、体力のある紙の媒体がどんどん減っています。一方のWEBメディアは、潤沢な経費の使える週刊誌が取材して得たネタを前提として記事をつくっているところも多い。もし、いつの日か週刊誌がなくなってしまったら、WEBメディアも大変なことになるんじゃないか、今後どうなっていくんだろう…というのは、常に考えていますね」