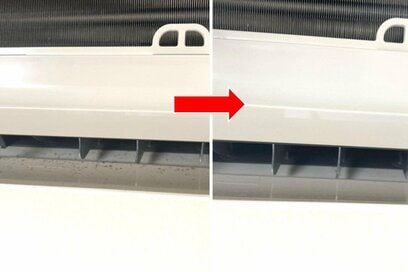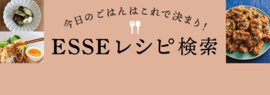高齢者施設にいた93歳の母を亡くし、悲しみに暮れていた作家の有川真由美さん。母の死後改めて見つめなおした「幸せ」と、ふと思い立ち訪れた奄美大島での日々について教えてくれました。
母との別れと旅に出るタイミング
奄美大島(鹿児島県)への旅は、一度あきらめた。
もともとは、秋に1か月ほど、奄美の龍郷町にある長期滞在者用の古民家を借りて、そこで本を執筆しようと予約していた。
しかし、高齢者施設にいてそれまでわりと元気だった母親が、たびたび高熱を出すようになって入院。私はすべての旅の予定をキャンセルした。コロナ禍でなかなか会わせてもらえず、携帯電話で話すこともままならない病状だが、近くにいたかった。
そして、ひと月、気が抜けない状態が続いたあと、母は眠るように旅立って行った。93歳になって11日後のことだった。
しばらくは母を見送ることで忙しかった。
告別式や役所への手続き、荷物の整理などがすんで、四十九日までやるべきことがなくなったとき、ふと寂しさが押し寄せるようになった。
朝起きたとき、おもしろいテレビ番組があるとき、母がいた病院の前を通り過ぎるとき、「あぁ、もう母には連絡できないのだ」「もう会うこともできないんだ」と胸が詰まる。
そして、ふと思ったのだ。
奄美大島に行こうと。
旅に出られるのは幸せなこと
喪中に不謹慎だと思われるだろうか。いや、そんなことはどうでもいい。
母なら「あら、いいじゃない。あなたがやりたいことなら」と言ってくれるはずだ。幼いころから、ずっとそう言ってくれたように。
母は私がどんな選択をしても反対したことがなかった。重症心身障がい児病棟の看護師をしていた母は、「子どもは生きていればいい」と昔から言っていた。親よりも先に亡くなっていく子どもたちを見てきたので、そんな境地になったらしい。どこで暮らしてもいいし、どんな仕事をしてもいい。ただし、幸せに生きて自分より先に逝くなと。
私が仕事を変え、住む場所を変え、旅するように生きてこられたのも、そんな母だったからだ。「母の近くに住む理由もなくなったな。つぎはどこで暮らそうか」とぼんやり考える。
私は意を決して「前に古民家を予約していた者ですが、まだ空いていますか?」と電話する。
「大丈夫ですよ。いつからいらっしゃいますか?」とNPO法人あまみ空き家ラボを運営するリエさんがあたたかく応えてくれる。途端に、心の時計が動き始めたような気がした。
私はイソイソと準備を始める。「3週間いないからやっておくことは?」「持って行くものは?」と、こんなときの頭の回転はすこぶる速い。
考えてみると、旅に出られるのは幸せなことだ。家族のこと、健康であること、仕事や経済的なこと…さまざまな状況が整って動けるのは、けっして当たり前ではない。
病床の母は覚悟ができていたのだろう。電話するとよく「私はほんとうに幸せ」と言っていた。「やさしい人と結婚できた」「定年まで看護師として働けた」「娘と息子が元気に育った」「いい施設に入れた」と、人生の幸せを数えるように。
そして、他界したあと、出てきた日記には、たくさんの日々の「幸せ」が綴られていた。「ご飯を完食した。美味しかった」「リハビリの先生と百三十歳まで生きよう!と言って笑った」「車椅子を押してもらって散歩した。気持ちが良かった」……。
幸せを見つけようとするくせは、きっと私のなかに引き継がれている。
自分の心に正直に生きた人だった。
娘から見ても、ほんとうに幸せな人だったと、つくづく思う。