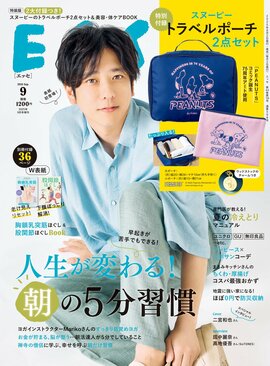片付けに関する情報発信などを行う整理収納アドバイザー・つうさん(40代)は、実家がゴミ屋敷という環境で育ってきました。「もったいないから捨ててはダメ」という祖母の教えにより、ものを捨てるのが苦手だったのですが、3つの思考の変化によって、片付けられるようになったそう。その経緯を詳しく語ります。
すべての画像を見る(全4枚)1:他人軸ではなく「自分の価値観」でものを選ぶ
以前の私は、ものを捨てるのがとても苦手でした。その理由を考えたとき、いちばんに浮かんだのが、「もったいないから捨てたらダメ」という、一緒に暮らしていた祖母の教え。幼少期からその言葉をずっと聞いて育ってきたので、大人になってからも「ものを捨てるのはダメなことなんだ」と思い込んでいました。
しかし、あるとき「もったいない」が口癖の祖母の暮らしを思い返してみたのです。家の中はものがどんどん増え続け、やがてゴミ屋敷状態になり、まともに暮らせるスペースもなく、とても不便な思いをしていました。
「そんな暮らしをしたいのか?」と自分に問いかけた結果、答えは「NO」。祖母のように「もったいない」とものを増やし続けるのではなく、自分にとって不要になったものは「捨ててもいい、手放してもいい」と選択肢を増やしました。すると、「自分の価値観」でもの選びができるようになり、少しずつ捨て活もスムーズになっていきました。
このことから、他人軸ではなく「自分はどうしたいのか?」ということを基準に、手放すもの・残すものを決める大切さに気がつくことができました。
2:ゲーム感覚で「捨て活」を楽しみ、慣れていく
いざ捨て活をしようと思っても、なかなかスムーズに進まない…ということが私自身もありました。そこで、捨て活に慣れるため「毎週土曜のゴミ出しの日に、不要なものを10個捨てる!」とノルマを設定することに。
10個と言っても、インクが出ないマジック、何年も使っていないコスメの試供品、賞味期限ぎれの食品など「こんなものもカウントしていいの?」と思うようなものでも、1個とカウントしていました。
すると、片付けが苦手な私でも、10個捨てるのは意外と簡単でした。週に1回くり返していくと「今週も10個クリアできた!」と、ゲーム感覚で捨て活を進めることができて、自然とものの要・不要の判断力も鍛えられていきました。