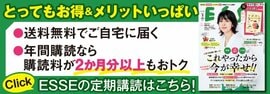どうしても必要なもの以外は、捨てても意外と大丈夫。水きりカゴやバスマット、ドレッサーは? 約10年、整理収納コンサルタントとして片づけの手伝いをしてきた須藤昌子さんが教えてくれました。
すべての画像を見る(全4枚)自分をラクにする片付けとは?
「ものを捨てなくては、片付かない」と感じる方は多いでしょう。「どれも大事なもののような気がして、捨てられない」と悩む声も聞かれます。また、「人が捨てたものを参考にしようと思うけれど、捨てられない」というジレンマに直面することもあるのではないでしょうか。
私は片付けに携わって約10年。「きれいにするためにグッズを使うこと」「不要なものを捨てること」そして現在は「自分をラクにするためのこと」というように、片付けの考え方が年を重ねるごとに変化してきました。
片付けに苦手意識を持っていらっしゃる40代50代の方々にも「捨てる苦しい片付け」から「自分の時間を機嫌よく過ごすための片付け」という意識に変えていくきっかけにしていただけたらと思います。
片付けというのは、自分をラクにすること。今回は、私が手放したものを例にお伝えしていきます。
1:「水きりカゴ」をクロスに替え、掃除の手間が減った
実家で使っていた水切りカゴ。私も結婚後、疑問を持たず当然のように使っていました。しかし、あるときから水のたまるトレーやカゴの汚れを毎日掃除することを苦痛に感じるようになりました。「自分の嫌なことをやり続ける必要があるのか?」という疑問が浮かび、水きりカゴを手放すことを考えたのです。
まず、水きりカゴの掃除と吸水性クロスを使うことのどちらが自分にとって苦痛が少ないのかを天秤にかけました。その結果、私は吸水性クロスを選ぶことにしました。そのおかげで、生活が少しラクに。
水きりカゴを使わないことで掃除の手間が省け、ワークトップを広く使うことができるようにもなりました。
2:「バスマット」をタオルに替えて洗濯の手間が減った
当然のようにバスマットを使っていました。「お天気のいい日でないと、厚く乾きにくいバスマットの洗濯はできない」と考えながら、毎日の洗濯に気を巡らせる自分に気づきました。
振り返ると、「お風呂の出入り口にはバスマット」「滑り止めのついたバスマットを使うものだ」という固定観念が私の中にあったのです。この「バスマット」という形にこだわることで、自分のタスクが増え、自分の行動に影響を与えていることに気づきました。
そこで、バスマットを使わない方法をと考え、乾燥が早い「タオル」を代用することに。その結果、バスマットの洗濯ができるかどうかにエネルギーを使う必要が減り、より大事なことに集中できるようになりました。
知らぬ間に根づいてしまった固定観念が、自分の行動を制限し、やらなくてもいいタスクを生んでいるという状況は、意外と多いと思います。そういったことに気づき、少しでもラクになれる方法を見つけていけたらと思います。