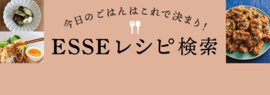親から子への支援。その記憶は、自分が親の年齢に近づくほどに理解を重ねていくものです。
ここではESSE読者が体験した、500円にまつわるエピソードをお送りします。
五百円札を同封した故郷からの手紙。母の愛にいつも励まされました
Yさん(鹿児島県・60歳)
すべての画像を見る(全1枚)昭和40年代、農村地域のどこもそうであったように、現金収入のある家は少なかった。わが家も、年に一度の米の収穫代と、父が近隣から頼まれる農作業や炭焼きなどでわずかな収入を得ていた。家計のやりくりも父が担い、煮炊き場につるされた大きな鍋の中から母が小銭を使い、ほそぼそと食卓を整えていた。
やがて農業も機械化が進み、母は世間の波にのって、日雇い労働に出るようになった。高速道路の工事現場で、お茶を出したり軽作業をしたりして現金を得る。自分の力で欲しいものを手に入れたいと考えたのだろう。最初の収入で布団用のタンスを買い、布団、食器棚と、次々に生活に必要なものを増やしていった。
●年を重ねるうち、母と同様に働く喜びを感じられるように
その頃、私は看護学校に通うため大阪へ出た。学校では教材や学費が無償で、そのうえ奨学金9000円が支給された。奨学金は生活費に充てるだけで精いっぱい。ほかの寮生に届く親からの仕送りや小包を目にすると、うらやましかった。
そんなとき母から、鉛筆で書かれた手紙が時折届くようになった。「お元気でしょうか」で始まる一枚の手紙。折りたたんだその中には、必ず五百円札がはさんであった。少ない稼ぎから、母はなにを思い、このお金を送ってくれたのか――そう考えると胸がいっぱいになり、泣かずにはいられなかった。末っ子で甘えん坊で、新しい土地や人になじむのにも苦労していた私に、母の手紙はどれほど励みになったことだろう。五百円札は、甘いものや、帰省のときの電車代に使わせてもらった。
日雇い労働に出る人が増えた頃、私は、茶つみや田植えを互いに手伝う、農村の「結いの精神」が薄れていく寂しさも感じていた。だがそれも、働きに出る母の生き生きとした顔を見るうち、考えが変わっていった。働いて収入を得ることは母の誇りだったのだろう。
母は3年前に他界したが、家庭をもち、母の年齢をなぞるようになった今も、手紙に同封されていた五百円札に母の深い愛と、働く女性としての喜びや誇りを思う。私も看護教員として誇りをもちながら、あと少し仕事を続けよう。