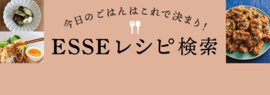3人組のロックバンド「THE ALFEE(ジ・アルフィー)」のリーダー、高見沢俊彦さん。初めて書いた小説『音叉』が、7月の発売後すぐに重版され、話題を呼んでいます。
執筆活動についてや、小説に込めた思いをESSE編集部が取材してきました。
小説を書けるなんて思っていなかったけど、書いてみたら、音楽と同じように自由でした
できたばかりのロック喫茶に、憧れのディスコ、海外ミュージシャンの初来日コンサートの興奮…。今年で結成45周年を迎えるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが初めて書いた小説『音叉』は、1970年代を舞台にした青春もの。学生運動の熱がまだ冷めやらぬ頃、バンドとしてプロデビューを目指す若者の葛藤が、鮮やかな光景と共に描かれています。
「当時はファッション業界でもan・anやnon-noといった雑誌が次々に創刊され、東京が急にカラフルになっていった記憶があって。自分に小説が書けるなんて思ってなかったけど、そこにあった風景の細部を書き出してみたら、物語の方がどんどん動いていったんです」
エネルギーあふれる時代の空気を象徴するのが、物語のなかでキラキラと輝く女性たち。
「あの頃から彼女たちの勢いには圧倒されっぱなし。男ってのは、その魅力に当てられてふらふらついていくだけですよ(笑)」
不器用で優柔不断。気持ちを伝えるのが苦手な主人公・雅彦も、女性たちとの出会いを通じ、少しずつ成長していきます。
「当時はメールなんてないから、文字で気持ちを確かめられない。生身の人間が対峙しながら、恋というものをその場でお互いに探している状態だったんです。それは友達同士の関係でも同じ。対面して初めて生まれるものがあるということを、この作品を通じて伝えたかったんです」
作中では心理描写も特徴的。感情が爆発したときには、エレキギターのチョーキング音が頭のなかで鳴り響いたり、独特の表現スタイルは、まさにミュージシャンならではの感性?
「いや、もちろんぼくの頭のなかで、同じことが起きているわけじゃないですよ(笑)。読みやすさというのは意識していて、具体的なイメージをもたせることで、感覚で読めるようにしたかったんです。活字離れと言われるなか、だれもが気負いなく入り込める小説を目指しました」
じつは、高見沢さん自身は「活字中毒」。幼い頃から家の本棚にずらりと並ぶ本を片っ端から読みふけっていたそう。
「教師だった父と8つ上の兄の本棚は、“大人の世界の扉”だった。ぼくのなかには、その扉を通じて得たものがたくさんあるんです。それらを言葉にしていけたらな、と思っています」
「小説も、音楽と同じように自由に書いていいんだ、と気がついた」という高見沢さん。頭のなかには、まだまだ書きたいことがあるそうで、次回作にも期待が高まります。
●『音叉』
学生運動の火も消えようとしていた1973年。大学生の風間雅彦は、高校からの同級生とバンドを組み、アマチュアコンテストで準優勝。プロデビューをもちかけられていたが、レコード会社側に厳しい条件を提示される。やりきれない気持ちを抱えたまま夜の原宿に足を向けた彼は、忘れられなかった女性と再会することに…。(文藝春秋刊 ¥1836)
【高見沢俊彦さん】
1954年、埼玉県生まれ。73年、大学在学中にTHE ALFEEを結成。リーダーとして楽曲のほとんどを手がける。コンサート通算本数は、日本のバンドとして最多の2690本を達成。ソロ活動や楽曲提供、ラジオ番組などでも幅広く活躍中