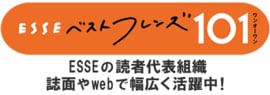<対処法:トラブルが起きたときは、直接会って伝えるのがベスト>
すべての画像を見る(全4枚)「今では『写真載せていい?』と確認するのがマナーにはなってきていますが、勝手に写真を載せられた、勝手に情報書かれてしまったなどは、ネットトラブルとしてよくあること。そうならないためにも普段から『ネットって怖いから写真はあげないようにしているんだけど、みんなはどうしている?』など周りがどういう使い方をしていて、自分はどうしているのか伝えておくといいでしょう」(高橋さん)
それでも載せられてしまった場合は直接会って、消してもらうようにお願いする方がよいそう。
「直接会って話せば、相手の反応に応じてフォローしやすいのでオススメです。また伝えるときは『ニュースでネットは怖いっていうの見たから』『(学校や園の)先生たちが心配しているみたいだから』など、納得しやすい要因を入れてやんわりと伝えることが、トラブルにつながりづらくなります」
●正義感が裏目に…気づけば自分がデマを加担する側に!?
「コロナに関するフェイクニュースが市内に流れたときに、友人からのLINEで入手した情報を信じてしまい、緊急性が高いと思って友人に流してしまいました。ただし、すぐにフェイクとわかってそれを伝えたので、大きなトラブルにはならずにほっとしました」(滋賀県・アルバイト・40歳)
「コロナで休校になった時期、40℃くらいでコロナが死滅するというスパムメールをママ友からLINEで送られてきました」(千葉県・主婦・41歳)
ニュースにもなっていましたが、「よかれと思って伝えた情報がことがじつはデマ」を、今回のコロナ禍で経験したという方も数名いました。情報が錯綜するなか、少しでも早く、そしてだれかのためにという正義感が、こういう形でトラブルのきっかけになってしまうのはとても悲しいもの…。まずは拡散するまえに信憑性を確かめるという作業が必要かもしれません。
<対処法:情報の信頼性を確認して、不明ならシェアしない>
「災害時は、不安で情報が錯綜するため、とくにデマの流布が増えることが知られています。多くの人がシェアしていても、みんながだまされている可能性もあるので、それだけで信用するのは危険です。いつ、だれが言っている情報なのかや、複数の情報を確認するというのが、デマにだまされないポイントです。必ず情報の出どころを調べて、信頼性を確認するくせをつけましょう」(高橋さん)
一般的に、省庁や公的機関、新聞社などの大手メディアなどが、発信している情報は信頼できる可能性が高くなるそう。
「その際、複数の情報発信元を確認するようにするとなお安心です。また災害時の情報は、そのときは正しい情報でも、時間が経つと状況が変わっていることもあるので、最新の情報かどうかも確認してください」
また、万一デマを流してしまった場合はどうするのがよいのでしょうか。
「TwitterやInstagramなどであれば削除の上、訂正したものを再投稿するといいでしょう。Facebookの場合は、謝罪コメントをつけた上で、もとの投稿を修正しておくことをおすすめします」
自分の使用しているアカウントは何のためか再確認を
「トラブルもゼロではないとはいえ、ネットを利用することはメリットも多いですし、私たちの暮らしから切っても切り離せないもの。だからこそ今一度何のために使うのか確認してみるのがいいと思います」と高橋さん。
ネットやSNSの主な用途は3つ。
・記録用・交流用
・情報発信や収集用
「本来何のためにどう使いたかったを確認することにより、どこまで公開するのか、どういったことまで発信したり書こうなど、ルールをつくることができます。ルールさえ決めてしまえば、あとから『あの写真アップしなければよかった』『こんなこと書かなければよかった』などという失敗を減らすことができると思います」
SNSはあくまでコミュニケーションのツールです。手軽にコミュニケーションが取れるからこそ、根本にある「人としてのマナー」を忘れずに、便利に使いこなしたいですよね。